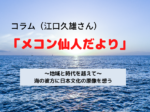- Home
- コラム「メコン仙人だより」(江口久雄さん), 特集テーマ記事
- コラム「メコン仙人だより」(江口久雄さん)第70話「老婆神から英雄神へ」
コラム「メコン仙人だより」(江口久雄さん)第70話「老婆神から英雄神へ」
コラム「メコン仙人だより」(江口久雄さん)
第70話「老婆神から英雄神へ」
黄河流域には紀元前2000年の昔から西王母なる老婆神が現われ、また紀元前1000年以上前に紅河デルタに居たタイ系のトン族は「千母の母」という老婆神を持っていました。大陸は元来、老婆神のエリアだったのです。済州島にもソンムンデなる老婆神が居て、島と山を造ったと伝えられています。この伝承は富士山を一夜で造った関東のダイダラ坊や、天の岩戸をちぎって投げたら信州に落ちて戸隠山になったというタヂカラオの別伝(それでタヂカラオは遠路はるばる筑紫国・紀ノ国を経て信州に向かう)と同系統の話で、発祥地は済州島でしょう。それにDAYIDALABOとTAJIKALAWOは、同じ言葉の方言形のように感じられませんか。
済州島に海人がやってきたとき、彼らが連れてきたソンムンデ婆さんが済州島を造ってくれたのです。しかし後代になって済州海人が筑紫国を経て紀ノ国・伊勢国に移住したときには、ソンムンデ婆さんの姿は無くタジカラオが移住民の中にいて戸隠山を造ったり、またダイダラボーの名で富士山を造っています。大阪人がキツネウドンをケツネウロンと訛るように、ダイダラボーはタジカラオが訛ったものでしょう。「追う」という言葉は標準語では「オ・ウ」ですが、出羽国では「ボ・ウ」と言います。身近なところでは「打つ」を「ウ・ツ」とも「ブ・ツ」とも言いますね。記紀では「手力男」と記されていますが、たまたまぴったりくる倭語があっただけの話でそんな意味ではありません。とはいえおかげで標準音が保存されたと言えます。記紀が成立した8世紀以降、タジカラオが関東の口承文芸の世界ではダイダラボーと訛っていったものでしょう。
タジマという言葉があります。新羅のアメノヒボコが身を落ち着けた但馬国のことですが、韓国語に「タジ(ダ)=堅固にする」という動詞があります。また韓国語で南のことを「マ」と言います。タジマとは韓国語(新羅語)で「堅固な南」という意味を持っています。その国には新羅人がたくさん住んでおり、日本海をはさんで往来があったと思われます。タジカラオのタジはタジマのタジで、カラは加羅のことでしょう。タジカラオは「手力男」ではなく「堅固な加羅の男」の意味で、スサノオ(男の中の男)のように新羅語+倭語の構造をもつ言葉でしょう。ふたつとも新羅語と倭語が分化していなかった時代にできた言葉に違いありません。
では「堅固な加羅の男」とは誰のことでしょうか。それは六加耶連合を造ったスヴァティのことです。海上権力をようやく形成した海人族にとって、洛東江の流域に入り込んだ国を造ったスヴァティは、それこそ土地や山や河を造り出した巨人に見えたのですね。漢に対しては「蘇馬諟」の本名を名乗り、領民に対しては首露王と名乗り、倭人や韓人からはタジカラオ(堅固な加羅の男)と呼ばれたものでしょう。
日本神話では大事な脇役として神となっています。英雄神が誕生したのですね。任那連合を再編成したスヴァティの威光の輝きに、済州海人は老婆神のソンムンデ婆さんを忘れてしまい、英雄神のタジカラオの崇拝に乗り換えたものでしょう。済州海人が倭国へ移住していった後、島に残る道を選んだ海人たちの伝承の中にソンムンデ婆さんは細々と生きつづけるだけになりました。倭国へ移住した済州海人はタジカラオという巨人と共に関東や信州に至り、富士山や戸隠山を造るのです。「ああ、あの山を造ったのはわれらがタジカラオ(ダイダラボー)ですよ」と吹いてまわったことでしょう。
スヴァティが造り出した国は、面積の広さはもとより文化も高く、ソンムンデ婆さんが造った済州島をはるかに圧倒したことは間違いありません。少なくとも済州海人は心理的に完全に圧倒されたことでしょう。この点が国土や山を創生する巨人の神を、同系統ながら済州島の老婆神(ソンムンデ)から倭国の英雄神(タジカラオ)に変身させた重要な理由になるのではないでしょうか。