北陸の歴史人物 「砂村新左衛門(1601~1667年)」(福井県鯖江市新町出身)
北陸の歴史人物 「砂村新左衛門(1601年~1667年)」(現・福井県鯖江市新町出身)

<写真上:「砂村新田開拓者 砂村新左衛門 顕彰碑」(東京都江東区南砂の富賀岡八幡宮境内)>(*2023年4月16日訪問撮影)
砂村新左衛門は、慶長6年(1601年)、越前国の新村で生まれた(現在の福井県鯖江市新町)とみられ、農民でありながら、開拓地の改良に興味を持つようになり、土木工事技術を身につけ、干拓工事による新田開発を目指し、壮年までは、越前国三国湊で土木事業に携わる傍ら、新田開拓の技術を習得し、やがて全国各地に赴き、江戸時代初期、プロの土木技術集団として、全国各地の新田開発に生涯を捧げる。代表的な開拓地は、関東本格進出の前に業績を上げた摂津の上福島(大阪市福島区)や、その後は武蔵の吉田新田(神奈川県横浜市)、相模の内川新田(神奈川県横須賀市)や砂村新田(東京都江東区)などが大きな業績。1667年に武蔵の砂川新田で死去するが、直前には遺訓も残している。
砂村新左衛門の生地については、以前は「新編相模国風土記稿」における「万治年中砂村新左衛門という者、摂州大阪上福島の人、管許を得て開墾す」という記述を元に大阪の出身であるとされていたが、1973年頃、福井藩の史書「続片聾記」の記述に「新左衛門は越前砂畑村の者にて」とあることを横須賀市の山内和子氏とその叔父鯖江市の高橋亮三氏が発見したことによって、福井県鯖江市の出身であると訂正された。江東区の「砂村新田跡」の史跡説明には、越前国砂畑村の出身と書かれているが、砂畑と呼ばれていたところは、村では無く、越前国の今立郡新村(現在の福井県鯖江市新町)の出身とされる。
この砂畑と新村の関係については、新村は、新左衛門の伯父にあたる福岡新兵衛(初代)が、穴田川と文室川(浅水川)の間の砂河原の荒れ地であった横越村と下新庄村と定次村の間の砂畑と呼ばれていたところを、慶長年間(1596年~1615年)の初期の16世紀末の頃、開拓し、後に「新」と名付けられた村(慶長3年(1598)には太閤検地を受け、高180石であったとされている)。初代福岡新兵衛の弟である初代福岡新左衛門(砂村新左衛門の父)は、兄とともに砂畑に来て、兄の福岡新兵衛の開拓事業を手伝いながら、新兵衛の屋敷内に分家を設け新村の新兵衛名義の田畑で耕作。その後、土木業を生業とするため、新兵衛家は水落村(現在の福井県鯖江市水落町)に分家を移す。溝手氏の初版の書籍で、砂村新左衛門(2代福岡新左衛門)の出身地を鯖江市水落出身と最初していたのは、このためだが、土木業を始めるために水落に分家を移したのが、初代福岡新左衛門となると、水落で出生という可能性も否定できないが、砂畑村の出身と書かれていることもあり、やはり、新村が生地で、2代新左衛門が土木業を始めるにあたり、水落に分家を移したという解釈。
尚、初代新兵衛と初代新左衛門の兄弟の祖父は、越前国の戦国大名・朝倉義景の家臣福岡三郎左衛門石見守(?~1573年)であったとも伝わる。1573年、朝倉義景(1533~1573年)が織田信長に追われて自害前、福岡三郎左衛門石見守は、朝倉義景から二人の息女を預けられ、息女の一人は本願寺教如に嫁ぐことが決まっており、豊原寺に息女を届ける途中、落ち武者狩りに遭い討死。このため、その子龍田は浪人となり、その龍田の子が初代新兵衛、新左衛門兄弟にあたると伝わる。
その後、さらに大きな仕事を求めて、九頭竜川河口の三国(現在の福井県坂井市三国町)に進出し商人の下請けやや土木工事請負をしながら新地開拓に必要な土木技術を磨いたとみられる。越前国福井藩第3代藩主・松平忠昌(1598~1645年)の時代に、藩の土木工事を請け負い業績を挙げ三国に別宅を構え、松平忠昌の許しを得て、砂村という姓を名乗ることになったといわれる。
三国(福井県坂井市三国町)では、後世まで砂村家舗と呼ばれた場所があるが、それは、福井藩が隣の丸岡藩との境界があり番所を三国に設ける必要があったが、番所や役人住居を作る場所も不足していたため、砂村新左衛門が木場と呼ばれていた材木置き場になっていた土地を開拓工事し福井藩に献上。福井藩有地になったその場所には、その後番所やそこに働く役人用の住居が建てられ、このエリアはその後、木場町と呼ばれ、番所裏の官舎の辺りが砂村家舗と呼ばれることになった。
代表的な開拓の一つで、地名にも砂村の名前が残ることになった万治2年(1659年)の砂村新田(現・東京都江東区砂町)開拓については、明暦の大火(1657年正月)後の江戸の再開発にあたっていた老中松平伊豆守信綱(1596年~1662年)から、霊岸島(現・東京都中央区新川)にあった歴代将軍から篤い信頼を得ていた霊厳寺の深川の地への移設の敷地の工事を見事に早く仕上げた(1658年完了)がきっかけ。この霊岸島は、松平忠昌が福井藩江戸中屋敷を構えた場所(松平忠昌はそこで逝去)で霊厳寺とも近い関係にあったはず。
■<主たる参考書籍> 砂村新左衛門の研究者・溝手正儀氏による以下の著書が詳しい。
2008年12月に自費出版「江戸時代初期、新田開発に生涯を捧げた 砂村新左衛門」及び、「増補改訂版 砂村新左衛門 江戸時代最強のデベロッパー」(2017年10月発行)
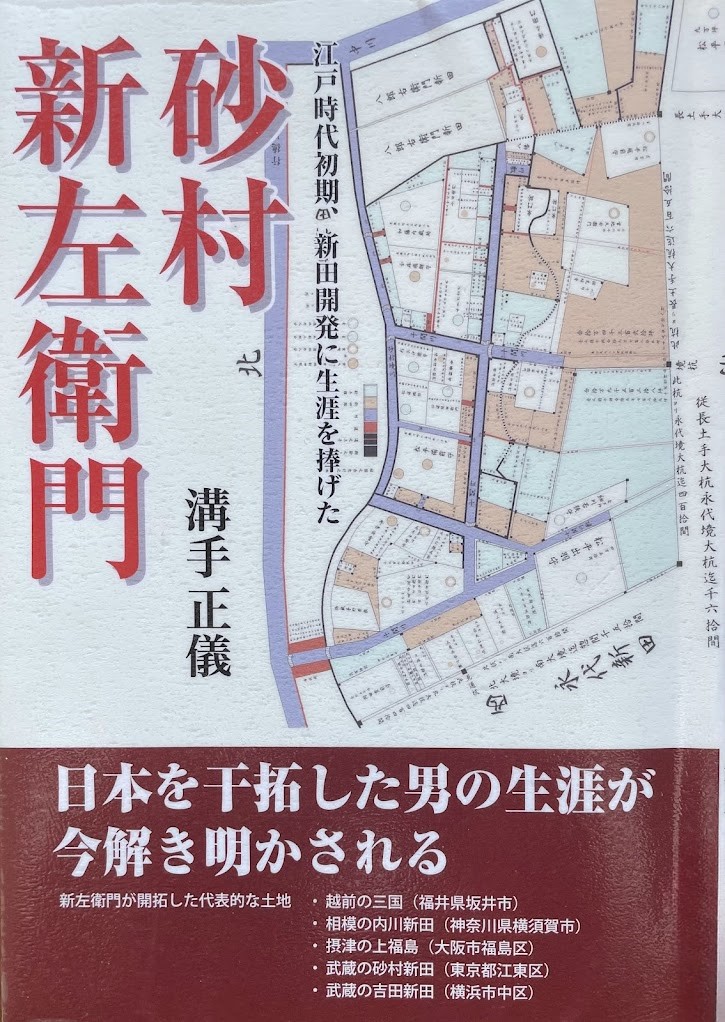
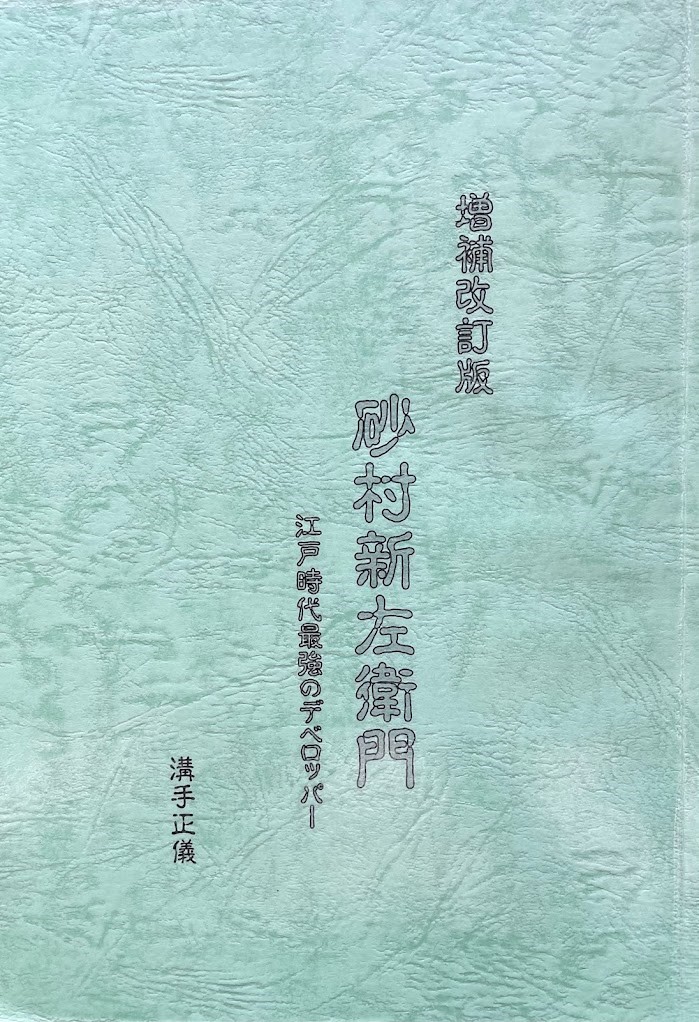
<写真下:福井県鯖江市新町 *2023年4月22日訪問撮影。鯖江市下新庄町から新町に入る地点と、鯖江市中野町出口から新町に入る地点。写真下の下の写真の左側が、文室川(浅水川)>













