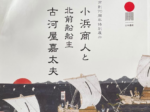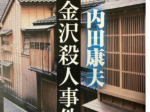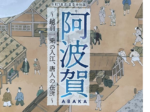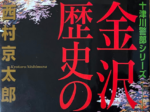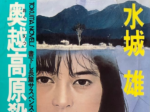- Home
- 北陸地域関連書籍, 「越」関連書籍紹介, 北陸を舞台とする小説
- 北陸を舞台とする小説 第28回 「砂冥宮」(内田 康夫 著)
北陸を舞台とする小説 第28回 「砂冥宮」(内田 康夫 著)
北陸を舞台とする小説 第28回 「砂冥宮」(内田 康夫 著)
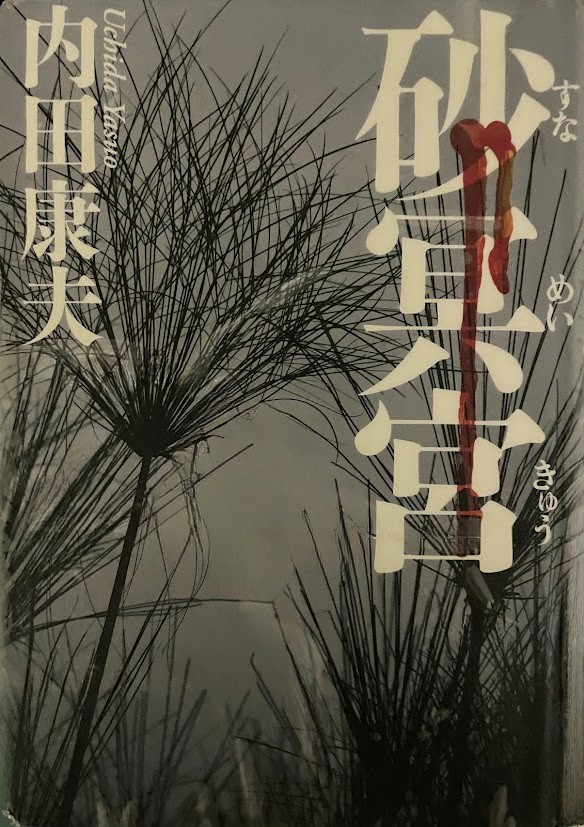
「砂冥宮」(内田康夫 著、実業之日本社、2009年3月発行)
<著者紹介>内田康夫(うちだ やすお)(本書掲載著者紹介より・発行当時)
コピーライター・CM制作会社経営を経て、1980年処女長篇「死者の木霊」でデビュー。『後鳥羽伝説殺人事件』で初登場した浅見光彦は、もっとも人気の高い探偵役である。著作は浅見光彦シリーズのほか、”信濃のコロンボ”竹村警部シリーズ、警視庁岡部警部シリーズなど多数で、2007年には総発行部数が1億部を突破、さらに第11回日本ミステリー文学大賞を受賞した。
<追記 *2018年3月逝去、享年83歳。1934年~2018年>
本書の著者・内田康夫(1934~2018)氏は、東京都出身で、コピーライターやCM制作会社の経営を経て、1980年に長編「死者の木霊」を自費出版。46歳で作家デビューし、1982年刊行の「後鳥羽伝説殺人事件」から始まった浅見光彦シリーズで人気に火が付いて以降、旅情ミステリーの代表的な推理作家として活躍。2008年日本ミステリー文学大賞受賞。本作品「砂冥宮」は、テレビドラマ化もされた内田康夫氏の代名詞ともいえる、名家の次男でフリーのルポライターの素人探偵・浅見光彦シリーズの作品の一つで、実業之日本社創業111周年特別書き下ろし作品。「砂冥宮」は、1995年から2018年にフジテレビ系で全53作品が放送された「内田康夫 サスペンス 浅見光彦シリーズ」の第44作(2012年放送、中村俊介版)でも取り上げられテレビドラマ化された作品。1952年(昭和27年)から、石川県河北郡内灘村(1962年の町制施行により現・内灘町)に広がる内灘砂丘値の大部分が在日米軍に接収され米軍砲弾試射場が建設され、反基地運動の先駆けとなる内灘闘争が起こったが、この内灘闘争が、本書「砂冥宮」の事件の大きな背景となっている。本作品は2009年3月に書き下ろしとして刊行されているが、本書のストーリーは2008年5月から7月までの期間で、内灘闘争のピークの1953年という、ストーリー展開時期の2008年から55年前の内灘(石川県内灘町)での出来事が鍵となる。
本書の最初の事件は、2008年5月13日、毎年5月に石川県小松市で行われている莵橋神社と本折日吉神社の春季例大祭で曳山子供歌舞伎で有名な「お旅まつり」前夜に、神奈川県横須賀市在住の77歳の男性・須賀智文が、歌舞伎「勧進帳」の舞台として有名な石川県小松市の安宅の関跡の先の海岸で男が殺され、翌朝、レストハウスの女性従業員に発見される。この殺害された男性・須賀智文は、家族に「金沢へ行く」と言い残して家を出て数日後に小松市の安宅の関跡で死体となって発見されたが、三浦半島の神奈川県横須賀市秋谷の須賀智文の家は、金沢出身の文豪・泉鏡花(1873年~1939年)の1908年発表の小説「草迷宮」の舞台のモデルとなった旧家。フリーライターの浅見光彦は、雑誌「旅と歴史」の特集「三浦半島」の取材で、泉鏡花の足跡を取材しに須賀家を訪ね、当主の須賀智文から話を聞き、三浦半島を取材した記事のゲラが出たので、その報告とチェックを頼もうと思って、須賀家に電話したことで、須賀智文が石川県小松市で殺害死体で発見され、家族が身元確認で石川県に出かけて不在ということを知る。その後、浅見光彦は、三浦半島の須賀家を訪ね、須賀智文の殺人事件が警察が予見している強盗殺人事件には思えず、事件の真相に近づくべく、浅見光彦は単身、石川県に向かい、小松署や死体遺棄現場の安宅の関を訪ね、須賀智文が最初に宿泊した金沢を訪ねる。
警察が、被害者の須賀智文が事件当日、金沢駅前のホテルを出て以降の足取りをまったく掴めないでいて、捜査は金沢から小松にかけての一帯で、情報の収集を行うことに専念するものの、成果があがらない中、浅見光彦は、金沢駅構内で、北陸鉄道浅野川線を偶然見つけ、目的もなく、始発の金沢から終点の内灘に向かう下り電車で、乗車中の地元のお年寄り同士の会話から、須賀智文が内灘を訪れていたことを知る。ただ、内灘の鉄板道路を抜けて、砂に吸い込まれるように、その先の海岸で足跡は途絶えていた。なぜ、須賀智文が、金沢へ来て内灘をなぜ訪れていたのか?という浅見光彦の疑問に糸口を与えたのは、内灘町役場の産業振興課の職員から紹介された、内灘の歴史に造詣が深い図書館の学芸員をしている中島由利子という50代半ばの女性と、横浜に一人暮らしをしている中島由利子の77歳の母親・中島峰子。中島由利子は、生まれも育ちも横浜ながら、内灘の歴史に惚れ込んで、内灘に根をおろしたという女性。中島由利子が内灘の町が好きなのは、母・峰子の影響があり、母が青春をかけた想いのこもった土地だった。
神奈川県横須賀市在住の77歳の男性・須賀智文が、石川県小松市の安宅の関跡の先の海岸で男が殺された事件で、須賀智文が金沢を訪ねた後、なぜ内灘を訪ねていたかということが分かりかけてきた中、最初の事件が起こった翌月の6月12日、富山県砺波市の小牧ダム、通称庄川峡のダムサイトに近い水面に、男性の死体が浮いているのを、庄川峡を走る遊覧船の職員が発見し警察に届ける。この第二の事件の被害者は、砺波警察署の調べで、石川県小松市に住む77歳の無職男性、大脇忠暉と判明。この大脇忠暉は、最初の事件の担当刑事で石川県警小松警察署刑事課の巡査部長で小松市出身・小松市寺町在住の轟栄の妻・幸子の父で、同じく小松市寺町在住。大脇忠暉は、地元の銀行の小松支店で定年を迎えていたが、内灘闘争の若い頃は、北陸鉄道の浅野川線で運転士をしていた。内灘闘争では、北陸鉄道浅野川線の労働者が、基地反対闘争に呼応して、列車を停めるストを敢行もしていた。55年前の内灘闘争の時のどういう人間関係が、55年経ち、何がきっかけで再び北陸の地で、77歳の高齢男性の連続殺人事件を引き起こすことになったのか、本書後半ストーリーで明らかにされていく。
本書で一番大きなテーマは内灘闘争であり、ストーリーの舞台としても一番重要なのは、内灘の町。内灘闘争は、内灘砂丘を舞台に取り組まれた戦後初の基地反対闘争で、1952(昭和27)年、在日アメリカ軍は、朝鮮戦争を背景に日本での砲弾試射場の提供を要求、政府は内灘を候補地とするが、これに対し地元住民は反対運動に立ちあがり、政党、労働団体、学生、知識人などの支援を得て、全国的に注目される基地闘争へと拡大。しかし、1953(昭和28)年3月からは試射が始まり、政府は試射場の永久使用を決定、これに対する住民の陳情や座り込みが繰り返されたが、その後、村内の分裂、試射の強行などによって運動は次第に弱まり、1953(昭和28)年9月、内灘村は試射場として使用を認め、最終的に、1957年(昭和32年)3月30日に、正式に試射場が返還されアメリカ軍が撤収したことで終息。本書でも、浅見光彦は、内灘の歴史に造詣が深い図書館の学芸員をしている中島由利子という50代半ばの女性から、内灘の着弾地観測所跡(権現森)に案内され内灘闘争の事を知り、すぐ近くの小濱神社社跡も訪ねている。昔は河北潟に面した貧しい漁村だったのが、砂丘の宅地化がどんどん進んで、人口も急増した内灘町の失われたものの歴史と、この半世紀で大きく変化した内灘の街の様子が紹介されている。
本書のストーリー題材に使われている北陸ゆかりのテーマは、内灘闘争以外では、著者の造語である本書タイトル「砂冥宮(すなめいきゅう)」のベースとなった金沢出身の文豪・泉鏡花(1873年~1939年)の1908年発表の小説「草迷宮」が使われている。泉鏡花は胃腸病静養のため、1902年(明治35年)8月から9月に、逗子(現・桜山5丁目付近)に短期滞在したのに続き、1905年(明治38年)7月から1909年(明治42年)まで再び逗子(現・逗子5丁目付近)に滞在。この逗子滞在期間に書かれた名作の一つが「草迷宮」で、この「草迷宮」の物語の舞台が、現・神奈川県横須賀市秋谷(あきや)。本書のプロローグでは、フリーライターの浅見光彦が、雑誌「旅と歴史」の特集「三浦半島」の取材で、泉鏡花の足跡を取材しに神奈川県横須賀市秋谷の泉鏡花の「草迷宮」の舞台のモデルとなった旧家を訪ねる場面からスタートする。浅見光彦は泉鏡花のファンというわけでないけれど、「草迷宮」の冒頭の一節だけは妙に頭にこびりついている、として、本書のプロローグの書き出しも、「草迷宮」の冒頭の文章がいきなり登場する。
最初の事件の被害者・須賀智文は、横須賀から金沢に出かけ小松市の安宅の関跡で死体となって発見されたが、その前に、金沢・尾張町の泉鏡花の生家跡の泉鏡花記念館を訪ね、金沢に1泊した後は、泉鏡花ゆかりの辰口温泉の最も由緒ある旅館「まつさき」に宿泊する予定になっていたとして、石川県能美市辰口の辰口温泉も、紹介されている。1883年(明治16年)12月、7歳の幼い頃に母を享年29歳で亡くした泉鏡花は、当時辰口温泉に住んでいた叔母にたいへん可愛がられ、叔母をたびたび訪ねるうちに、辰口温泉で働く美しく艶やかな芸妓さんたちの姿を通して、女性に対する感性を磨いていったとも云われていて、泉鏡花は辰口温泉の旅館「まつさき」に逗留しながら当時のまつさき旅館を舞台とした『海の鳴る時』を執筆している。
本書のストーリーの展開場所としては、石川県内灘町とともに、石川県小松市も重要で、最初の事件の死体発見現場が、歌舞伎「勧進帳」の舞台として有名な石川県小松市の安宅の関跡の先の海岸となっているが、その最初の事件が起きた日は、毎年5月に石川県小松市で行われている莵橋神社と本折日吉神社の春季例大祭で曳山子供歌舞伎で有名な「お旅まつり」前夜。小松市にある8つの町(大文字町、西町、龍助町、寺町、京町、材木町、中町、八日市町)は、毎年5月に行われる「お旅まつり」において、曳山子供歌舞伎を奉納することで知られていて、本書の主要な登場人物の1人である石川県警小松警察署刑事課の巡査部長の轟栄や、義父の大脇忠暉は、その8つの町の一つである小松市寺町在住。小松市寺町は、加賀藩2代藩主の前田利常が小松城の鬼門を鎮護するために、市内にあった多くの寺院を集めたことに由来する歴史ある地域。本書のストーリーの展開場所として、石川県内では、地元警察が最初の事件の被害者が金沢から内灘に立ち寄っていたとの情報から、その先の行方を追うために、内灘方面での警察による聞き込み捜査が、内灘町とは河北潟を挟んで東側にある津幡町と、内灘町に南接する金沢市大野町にまで範囲が広げられたことにより、金沢市大野町にも、多少触れられている。金沢市大野町は大野川の河口を挟んだ南側にも町域があり、北岸の大野町にはオイルタンクなどの工業施設が多いが、南岸側は大野川河口の港として古くから開けたところで、江戸期から続く醤油醸造業者が多く、ここの独特の風味を持つ醤油は「大野醤油」として全国的に知られた存在だと紹介されている。
目次
プロローグ
第一章 お旅まつりの夜
第二章 鉄板道路
第三章 砂の記憶
第四章 庄川峡へ
第五章 迷宮への道程
第六章 四番目の男
エピローグ
自作解説 ーあとがきに代えて
解説 山前 譲
<主なストーリー展開時代>
・2008年5月~7月
<主なストーリー展開場所>・
・石川県(小松市、内灘町、能美市の辰口温泉、金沢市、金沢市大野町) ・富山県(砺波市庄川町、富山市)
・横須賀市秋谷 ・東京(三鷹市、上中里) ・宮城県(仙台市)
<主な登場人物>
・浅見光彦(東京都北区在住のフリーの雑誌ルポライター)
・須賀智文(神奈川県横須賀市秋谷の須賀家の77歳の主)
・須賀綾香(須賀智文の24歳の孫娘で、横浜の大学の大学院生)
・轟栄(石川県警小松警察署刑事課の巡査部長で小松市出身で小松市寺町在住)
・轟幸子(轟栄の妻)
・大脇忠暉(轟幸子の父で小松市寺町在住。賀能銀行の小松支店で定年。その前は北陸鉄道勤務)
・須賀春男(須賀智文の長男で、須賀綾香の父)
・須賀幹子(須賀春男の妻で、須賀綾香の母)
・杉江誉子(しげこ)(須賀智文の姉で西東京市在住、三鷹の杏林大学附属病院入院中)
・佐々木律子(安宅の関跡のレストハウスの女性従業員)
・川原淳佑(安宅の関跡のレストハウスの店長)
・大脇克子(轟幸子の母)
・轟洋一(轟栄の父親で富山県礪波市在住。もともとは小松市出身で、礪波に本社がある運輸会社本社の取締役)
・轟富江(轟栄の母親で富山県砺波市在住)
・轟真純(轟栄の小学6年の娘)
・轟勇人(轟栄の息子)
・中島由利子(内灘の図書館の学芸員で50代半ばの生まれも育ちも横浜の女性で私生児)
・中島峰子(中島由利子の77歳の母親で、横浜の山手に独り暮らし)
・水城信昭(中島峰子の学生時代の恋人で内灘闘争時に病死。仙台出身)
・水城美智絵(水城信昭の妹で、旧い漢方薬の店を継ぐ)
・水城千晶(水城美智恵の息子の嫁)
・黄金井達也(賀能銀行の会長で80歳。内灘に別荘所有)
・酒井麻美(黄金井会長の秘書)
・崎上進吾(賀能銀行取締役調査部長)
・崎上ゆかり(崎上進吾の妻)
・関谷邦男(昔は庭師の横須賀市の造園業会社の社長)
・関谷健太郎(関谷邦男の息子で造園業会社の副社長)
・松崎社長(辰口温泉の旅館「まつさき」の6代目社長)
・JR金沢駅前のホテル日航のフロント責任者
・金沢市尾張町の泉鏡花記念館の受付女性
・中根正人(石川県警捜査一課の警部で事件の捜査主任)
・滝川洋(石川県警小松警察署刑事課長)
・小池刑事(石川県警小松警察署刑事課で。高校時代は体操部に所属)
・小松警察署刑事課受付の女性
・北陸鉄道浅野川線の金沢駅駅員
・松原(津幡警察署の内灘交番の巡査長)
・細呂木谷正義(内灘の金沢医大病院に北陸鉄道浅野川線に乗り通院する77歳の老人)
・金沢医大病院の女性職員
・内灘町役場の産業振興課職員
・庄川遊覧船乗り場の職員
・庄川遊覧船の待合室の売店の女性
・上里亮人(富山県砺波署の40歳前後の警部補)
・西譲二(黄金井会長のボディガード)
・高橋和宏(黄金井会長のボディガード)
・浅見陽一郎(浅見光彦の兄で警察庁刑事局長)
・和子(浅見陽一郎の妻)
・雪江未亡人(浅見光彦の母)
・須美子(浅見家のお手伝い)
・藤田(雑誌『旅と歴史』編集長)
・平塚亭のおばさん(東京・上中里の平塚神社境内にある和菓子店)