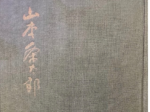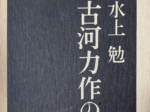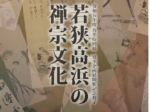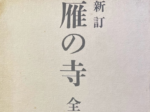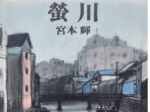- Home
- 北陸地域関連書籍, 「越」関連書籍紹介, 北陸対象の図録・資料文献・報告書
- 北陸関連の図録・資料文献・報告書 第15回 森山啓生誕百年記念「森山 啓 の記録 ーその人と文学ー」(編集: 森山啓生誕100年記念誌発行委員会、発行: 小松市立図書館 )
北陸関連の図録・資料文献・報告書 第15回 森山啓生誕百年記念「森山 啓 の記録 ーその人と文学ー」(編集: 森山啓生誕100年記念誌発行委員会、発行: 小松市立図書館 )
北陸関連の図録・資料文献・報告書 第15回 森山啓生誕百年記念「森山 啓 の記録 ーその人と文学ー」(編集: 森山啓生誕100年記念誌発行委員会、発行: 小松市立図書館 )
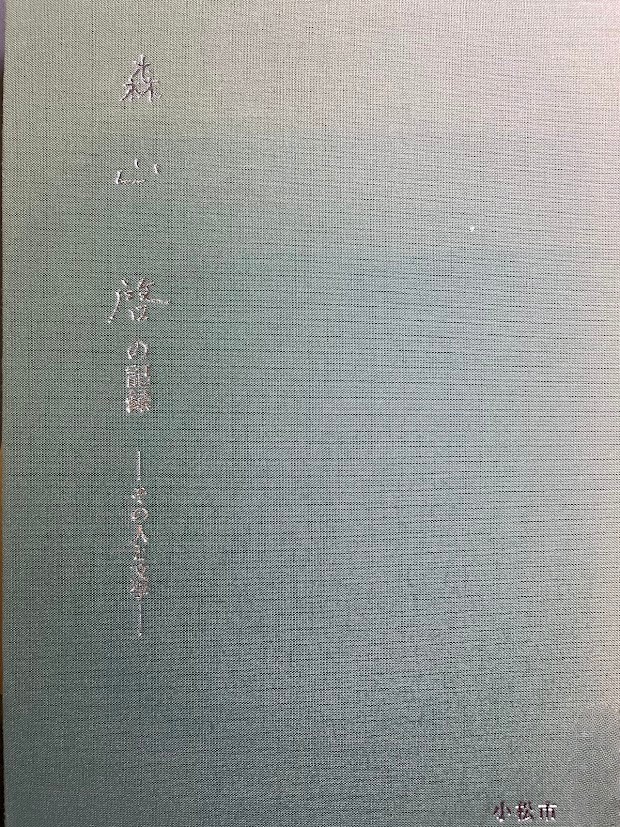
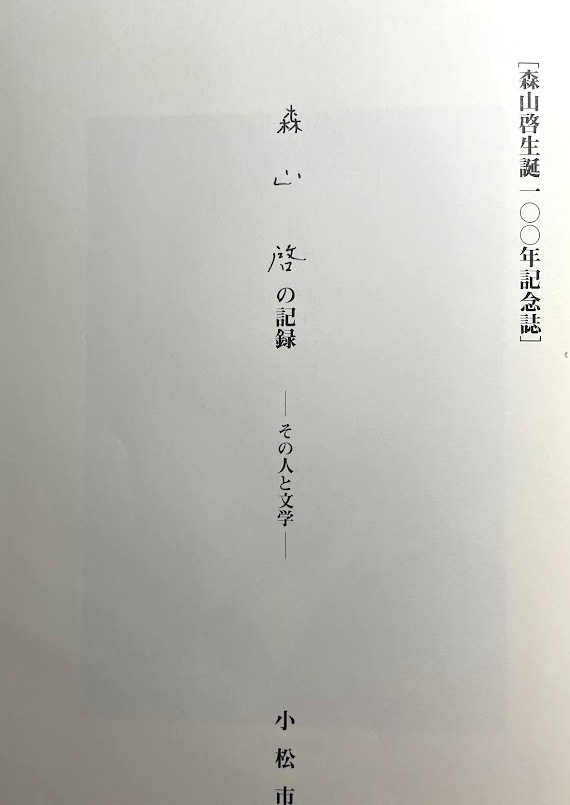
森山啓生誕百年記念「森山 啓 の記録 ーその人と文学ー」(編集: 森山啓生誕100年記念誌発行委員会、発行: 小松市立図書館、2004年10月発行)
森山啓生誕100年記録誌「森山 啓の記録 ーその人と文学」
<執筆者及び担当部門一覧>(五十音順)
井口 哲郎(財団法人石川近代文学館理事):担当第一部「森山啓の記録」第二章「森山啓の年譜」
金戸 隆幸(小松社会教育協会副会長):担当第三部「森山啓と小松の文化」
正和 久佳(小松市立博物館専門委員):
担当第二部「森山啓の文学」第一章「著作目録」第二章「文学作品の世界」
西口 嘉昌(小松文芸懇話会会長):担当第一部「森山啓の記録」第二章「文芸抄史」
森松 和風(森山啓・三男):担当第一部「森山啓の記録」第一章「追憶」
石川県小松市に大変ゆかりのある作家・森山啓(もりやま・けい)(本名:森松慶治、1904年~1991年)は、平成3年(1991年)7月26日に、入院先の石川県松任市の病院で、呼吸不全と腎不全のため逝去(享年87歳)。石川県小松市立図書館にて、その時に緊急で「森山 啓 追悼特別展」が、平成3年(1991年)10月25日から11月10日までの15日間、開催されているが、没後13年にあたる2004年が1904年生まれの森山啓の生誕100年にあたるということで、小松市当局の肝いりで、「森山啓生誕百年記念事業」が企画され、本書は、平成16年(2004)10月に小松市立図書館が発行した森山啓の生誕100周年記念誌。森山啓がその生涯に創作した文芸作品の全てを網羅した「著作目録」にあり、併せて、森山啓の人となりを綴り、森山啓研究のための記録を次代に伝えるリングの役割を持たせた本にすることが本書編纂の目的で、3部5章の構成。生前の1975年(昭和50年)11月9日、石川県小松市安宅町住吉神社境内に、森山啓文学碑が建立され、没後の1997年(平成9年)「森山啓文学選集(1)(時代小説編)」が出版され、2000年(平成12年)には、小松市文芸懇話会の協力で、小松市立図書館に「森山啓記念室」が設置されている。
森山啓(本名:森松慶治)氏は、富山人出身の両親(父親は本礪波郡野尻村出身で現南砺市、母親は西砺波郡戸出町出身で現高岡市)のもと、旧制中学教師であった父親が富山県立富山中学から明治36年(1903年)に新潟県村上中学に転任となり、新潟県岩船郡村上本町(現・村上市)で1904年(明治37年)3月10日に生誕。その後、父親が新潟県立高田中学の教師に転任し、新潟県内の高田市に転居するも、新潟県での生活は生後4歳半までで、1908年11月末には、父親が富山県立高岡中学に転任により、家族で新潟県高田から富山県高岡に移住となり、その後は小学2年修了の1912年春までの約3年半は富山県高岡市在住。その後は父親が福井県立福井中学の教師となり、森山啓 氏は、1912年4月の宝永小学3年から1916年に福井中学に首席で進学。1920年秋、金沢の第四高等学校に入学までの約8年半は家族と共に福井市内で生活。2度の福井市の実家での長期の病気休学もありながら金沢で第四高等学校学生生活を過ごし、明治後半・大正時代の幼少から小学・中学・高校の学生生活は、富山・福井・石川の北陸各地で暮らし北陸に非常にゆかりがある作家。
1925年4月、東京帝国大学文学部哲学科美学科に入学。東大美学科在学中に、福井県坂井郡高椋村(現・坂井市丸岡町)出身の中野重治と親交を持ち、プロレタリア芸術運動に携り、1928年に大学を中退。弱体化しているプロレタリア文学運動立て直しの有力な担い手の一人として、大変な生活苦の中で華やかな文学的活躍は注目されるも、その後「転向」。1941年(昭和16年)8月、夫人みよさんの生まれ故郷で家族の待つ石川県小松市に疎開し移住。1942年には『海の扇』で新潮社文芸賞を受賞。その後も長く石川県小松市で作家活動を続けていたが、1978年10月、40年近く住んだ小松を離れ石川県松任市(現・白山市)に転居し1991年に松任市の病院で死去。1925年から1941年の16年間の期間は東京ながら、37歳の1941年から87歳の1991年病没までの後半生の約50年も、北陸の石川県(小松市・松任市)で長らく過ごしている。
刊行の辞 ~詞藻豊かに脈々と~ 小松市長 西村 徹
今年は、作家森山啓生誕百周年にあたります。先生は小松市にたいへんゆかりが深く、戦前、戦中、戦後を通じて一貫して中央の文壇と距離を置く気骨さを示す一方、北陸で、とりわけここ小松で38年もの長きにわたって居を構え、数々の名作を世に送り出されました。
森山文学には、多くの読書人が指摘されておりますように、家族や貧者に寄せる限りない愛があり、自然や命あるものへの慈しみなど、まさに至情に満ちており、作品の随所に見られる小松弁の懐かしさも読者の心を和ませてくれます。
本市では、先生の数々の業績を称え、小松との馴染み深い関わりを後世に残し伝えようと市立図書館に森山啓記念室を設置したり、講座や作品に親しむ集いを開催したりするなど、様々な企画を実施してまいりました。この記念誌の発刊は、その集大成ともいうべき意義深い事業であります。
目を転じてみれば、地方の文化、殊に小松の文芸の振興に果たされたご功績にも多大なものがあります。昭和21年、戦後間もない頃に呱呱の声を上げた小松文化連盟の結成にご尽力され、昭和30年に「小松文芸」が創刊されて以来、後進への指導や助言などによって、多くの文人を育てられました。こうして師の馨咳に接し、薫陶を受けられた方々が、脈々と小松文芸懇話会に引き継がれ、言語芸術の裾野が広がっていることも心強い限りと存じております。
また詩人として、加賀一円の高等学校や中学校の校歌の作詞もなされていて、郷土の美しい風物を謳い上げる詞藻の豊かさは、今も清澄な響きを持って歌い継がれています。
ふるさとが生んだ作家森山啓は、これから広く各層の市民の皆様に親しんでいただくことになるわけでございますが、かつて教鞭をとられた小松農・商学校の後輩にあたる県立小松商業高等学校生徒の有志を中心に、近年中・高校生の間で森山文学への関心が高まってきていることは誠に喜ばしい限りでございます。時代は違っても、人の世の生き方を求める有り様が今の若い人達の共感を呼ぶからではないでしょうか。
今回の記念誌の発行を契機に一人でも多くの方々に、郷土が生んだ偉大な作家の生涯とその作品を通して、今を生きる自らの生き方を振り返っていただくことができるなら、誠に意義深いことと存じます。
最後になりますが、記念誌の刊行にあたり、お世話、ご尽力をいただきました関係各位に、厚くお礼と感謝を申し上げまして、刊行の言葉と致します。
本書「第一部 森山 啓の記憶」の「第一章 追憶」は、森山啓 氏の三男・森松和風 氏による、家族ならではの追憶文章と貴重な家族の写真を掲載。まず、昭和34年(1959年)前後の家族の様子が紹介されており、中でも、森山啓 原作「若いいのち」の映画化(「雑草のような命」)が決まった日の父・森山啓の様子が印象的。昭和38年(1963)1月豪雪に古城町の借家の雪下ろしの父子の思い出、更に小松市古城町から1966年10月に小松市白松町の市営住宅を購入した新居の思い出に続いて、1989年発表の青春自伝小説「谷間の女たち」に頻繁に登場する森山啓の姉せき(森山和風氏の叔母)について、まとまった文章が掲載されている。最後には、1978年11月に移転した最後の住みかとなる松任市の新居と、その移転直前の頃の話にも触れられている。尚、森山啓 氏の長女・けい子(恵子)は、1930年8月誕生。1933年1月、尿毒症のため死亡。長男・健介は、1935年5月誕生。次男・勤は、1940年1月誕生するが、1943年10月に3歳で病没。三男の森松和風 氏は、長女・けい子、次男・勤の病没後の1948年8月に誕生。
本書「第一部 森山 啓の記憶」の「第二章 森山啓の年譜 附 文芸小史」では、数々の写真とともに、詳細な年譜が約30頁強にわたり、まとめられているが、「年譜」作成に当たっては、単にその人生をたどるだけでなく、森山啓が、相次ぐ肉親との死別、生活苦、思想上の悩みなど、不幸な「運命」との遭遇の連続で、そうした「運命」にいかに対処していったか、そしてそこから、いかにして森山啓の「人間愛」が生まれていったかということを常に念頭に置きながら進めたとのこと。この年譜では、明治37年(1904)の森山啓(本名:森松慶治)出生から、平成3年(1991)7月、呼吸不全と腎不全のため死去までの年譜に加え、平成10年(1998)10月、妻・みよ死去のことも含め、本書発刊の平成16年(2004)没後13年までの関連出来事も加えらえている。
本書「第二部 森山 啓の文学」の「第一章 著書目録」では、本書巻頭に、本書編纂の目的は、森山啓がその生涯に創作した文芸作品の全てを網羅した「著作目録」にあったと書かれているだけあって、70頁以上にわたる膨大な著書目録の記録。森松慶治が、森山啓の筆名で執筆を開始した昭和2年(1927)から没年の平成3年(1991)迄に発表した文芸作品を、初発表時を中心にして年度別に古い年代から現在に向けて順列に並べており、この目録に収録した初発表と思われる森山啓著作品は、小説類256点、詩132点、評論・随筆(新聞を含む)801点。著作目録の最初の作品は、昭和2年(1927)年末に、「プロ芸」(日本プロレタリア芸術同盟)に参加し、雑誌『プロレタリア芸術』12月号に発表した詩の処女作「犠牲者の身内」。絶筆は、回想録の小説「楽しい長寿への茨道」で、没後の11月に『新潮』誌上に発表されているが、この口述筆記の絶筆作品については、「第一部 森山 啓の記憶」の「第一章 追憶」にて、森松和風氏が思い出を記している。
本書「第二部 森山 啓の文学」の「第二章 文学作品の世界」では、「著書目録」担当の正和 久佳 氏(小松市立博物館専門委員)が、作品を選んで、表題、成立、登場人物、梗概、解説を加えた作品紹介が行われ、作品への興味を沸き起こしてくれている。森山啓が文壇に登場するのは詩人森山啓としてで、続いて文芸評論家に変身。次いで森山啓が渇望した小説家森山啓への転身は、本人によれば、昭和12年『文芸』2月号に発表した「収穫以前」とのことだが、それ以前にも小説は書いていて、森山啓が書いた小説は、確認できる限り、ジュニア向け小説を入れて256作品。この編では、「美しいもの・醜いもの その一」「風の吹く道」「流年」「萱原」「山徑」「遠方の人(谷津傳八・夏路・潤吉の物語)」「若いいのち」「三郎と若枝」「若い二人と母」「若葉と霜葉」「渚(なぎさ)」に、時代小説の「泡沫ー市之丞と青葉」「姿舟」「野菊の露ー能登麦屋節考」「蘭の露」「春路の歌」「関所破り」が紹介され、更に昭和11年(1936)発表の2篇の詩「むかし或国に或男があった」「私の伴侶に」が収められている。
森山 啓 氏は、小松市に長らく住んだ著名な作家というだけでなく、地方文化の向上のために、特に小松市の文化活動の先頭にたってきたということも特筆すべきことで、本書「第三部 森山啓と小松の文化」では、小松の地方文化との関わりについて紹介されている。森山 啓 氏の戦後まもない昭和21年(1946年)小松文化連盟の結成に尽力し会長に就任。昭和30年(1950年)総合文芸誌「小松文芸」の発刊以来、昭和33年(1958年)2月「小松文芸懇話会結成もあり、後進への指導や助言などにより多くの文人を育てる。森山 啓 氏は、昭和16年(1941)8月、夫人みよさんの生まれ故郷の小松市に転居。小松市の大和町から上牧町、梯町(1946年5月~)、古城町(1951年夏~)、白松町(1966年12月~)と、1978年11月に松任市に移るまで約37年間、小松市に在住。この編では、昭和63年(1988)4月、妻みよさんの退院祝いの買い物の途中に被害に遭った交通事故のこと、平成3年(1991)7月28日の葬儀、逝去後の遺作展開催、和風氏とみよ夫人による蔵書の小松市への寄贈と小松市立図書館内の「森山啓記念室」誕生の経緯なども記されている。
目次
題字「森山 啓」は自筆原稿の署名より採取した。
森山 啓の肖像
森山 啓 小松市文化章(盾・記念写真)
発刊の辞・・・小松市長 西村 徹
発刊に寄せて・・・小松市教育長 矢原珠美子
第一部 森山 啓の記録
第一章 追憶・・・森松和風
第二章 森山 啓の年譜 附 文芸小史・・・井口哲郎・西口嘉昌
第二部 森山 啓の文学
第一章 著作目録・・・正和久佳
第二章 文学作品の世界 =梗概と解説=と=詩=・・・正和久佳
索引
第三部 森山 啓と小松の文化
先生と歩んだ日々・・・金戸隆幸後記