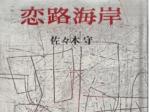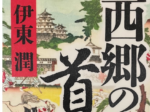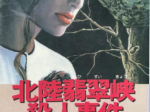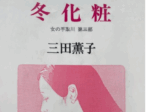- Home
- 北陸地域関連書籍, 「越」関連書籍紹介, 北陸ゆかりの作家による作品
- 北陸ゆかりの作家による作品 第5回 「緋は紅よりも ー 女の手取川 第二部」(三田 薫子 著、創林社)
北陸ゆかりの作家による作品 第5回 「緋は紅よりも ー 女の手取川 第二部」(三田 薫子 著、創林社)
北陸ゆかりの作家による作品 第5回 「緋は紅よりも ー 女の手取川 第二部」(三田 薫子 著、創林社)
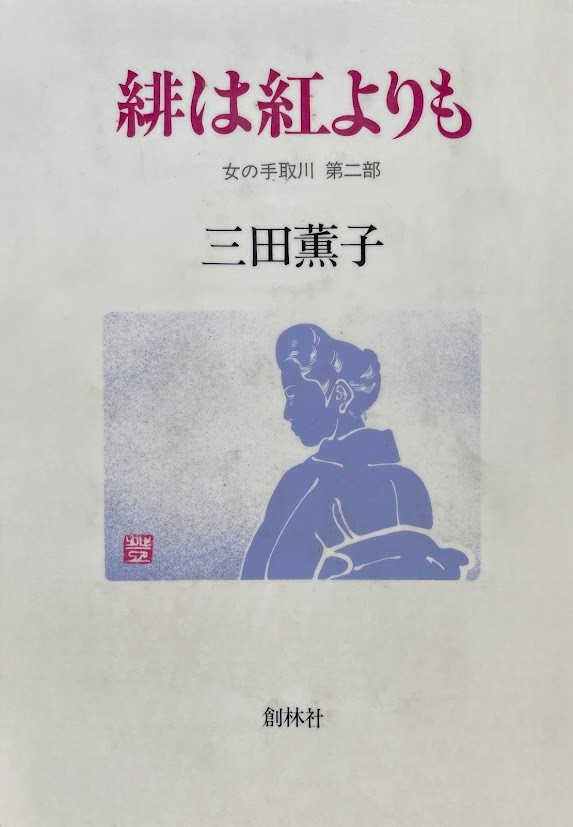
「緋は紅よりも ー 女の手取川 第二部」(三田 薫子 著、創林社、1985年7月発行)
三田 薫子(みた・かおるこ)<本書著者紹介より、本書発刊当時>
1944年、石川県石川郡美川町生まれ。著書に『女の手取川』(創林社)。現在、金沢市在住
本書「緋は紅よりも ー 女の手取川 第二部」(三田薫子 著、創林社、1985年7月発行)は、白山に源を発する日本有数の急流河川で日本海に注ぐ一級河川の手取川河口の港町・美川町(旧・石川県石川郡美川町、現・石川県白山市美川地区)を舞台に、美川町に生まれ育った女性「七代」を主人公とする大河小説で、「女の手取川 万屋模様」に引き続き刊行された「女の手取川」三部作の第二部。本書の第二部に続くのが、「冬化粧 女の手取川 第三部」(1986年6月発行、創林社)。著者の三田薫子 氏は、本書の舞台となる、石川県石川郡美川町に生れ育ち、著者の母をモデルとした作品で、後半生は小松市に長らく住んだ著名な作家で地方文化の向上のために特に小松市の文化活動の先頭にたってきた作家・森山啓 (1904年~1991年)氏に師事して作家活動を始め、「女の手取川 万屋模様」が処女作で代表作の一つ。
森山 啓 による評
■長編「緋は紅よりも」は、北陸のきびしい風土に耐えて生き抜く女を中心に、伝統の風習を打ち破って奔放に生きようとした魅力ある女の典型と、伝統の風習をそのまま受け入れる忍従の度が過ぎて狂い出した女の典型とを描いている。大勢の登場人物のすべての性格と生きざまを、その家庭、衣服、食性格、および環境としての美川町の風習のすべてにわたって、驚くべき筆力で活写している。想像力が豊かな物語の進行とその大破局も興味深い。(森山 啓)
本書の主人公は、石川県石川郡美川町の中町通りの商人宿屋と料理屋、魚商を兼ねた「万屋(ばんや)」の娘として、1921年(大正10年)に生まれた万屋七代。「女の手取川」第一部では、父・平作、母・すまの間の男6人、女3人の次女として、七代が9歳の正月を迎える昭和5年(1930年)から、同じ美川町の大正通りに嫁ぐ22歳の年の昭和18年(1943年)春までの時代が描かれたが、第二部の本書では、万屋七代が同じ美川町の大正通りにある農業機械などを扱う商家・加賀屋に嫁ぎ加賀屋七代となった22歳の年の昭和18年(1943年)春から、生母・万屋すまが狂い手取川河口で入水自殺をした後の五七日の供養(亡くなった日から35日目に行われる法要)も終えたばかりの37歳の年の昭和33年(1958年)1月までの時代が描かれている。7歳年上の29歳の大海。
「女の手取川」第一部では、美川町の中町通りの料理宿・万屋に生れ、少女から娘に成長していく主人公・七代を中心に、賑わい活気があり忙しい「万屋」の大家族をはじめ、「万屋」で働く人たちや、美川町の地域の人ちの人間模様が、昭和初期から昭和十年代の濃密な美川町の地方風俗とともに、生き生きと描かれていたが、本書「女の手取川」第二部では、美川町一番のにぎやかな大通りである大正通りの真ん中にあり、農業機械や綰物(わげもの)を扱っている商家・加賀屋に嫁ぎ、万屋七代から加賀屋七代となり加賀屋での嫁、妻、母としての暮らしぶりが描かれる。七代の夫は、大正3年(1914年)生まれで七代より7つ年上の加賀屋の長男・大海(たいかい)。21歳の時に現役召集で、近衛師団から、満州国ハルピンに派遣され、次に召集を受けたのが中支。召集解除満期後はA航空会社に勤めていた時に結婚。結婚した1943年の年には、また愛知県一の宮の近衛師団千葉鉄道連隊名古屋管内分遣隊へ配属される。七代が嫁いだ結婚当初は夫の3人の弟も同居で、小松町のK製作所に勤めに出る次男と三男に金沢の高等学校に行く四男がいるが、いずれもその後召集となる。
加賀屋での家族との生活では、夫の加賀屋大海より、加賀屋の女主である姑の加賀屋ぜらが存在感が大きく強烈で、嫁としての加賀屋七代が非常に気の毒なくらい、加賀屋の嫁に対し厳しい。第一部での生家での娘時代の暮らしが暖かく懐かしく賑やかで楽しいものに余計思えるくらい、対照的に、第二部の本書では、嫁に対して、事あるごとに厳しすぎる姑との関係は、かなり緊張を強いるもの。姑のぜらの嫁の七代に対する、理不尽と思える数々の言動に対しても、夫の加賀屋大海は、実母に対し、妻の七代をかばう気配はなく、舅の正太朗は、人望も厚く、地区のいろんな役も務め、働き者で一代で町の大通りのど真ん中に店舗を構えた男で、嫁の七代にはとても優しく気配りもできる人ながら、なぜか、妻のぜらには、頭が上がらないのか、強くたしなめるような言動は無い。姑ぜらの数々の奇行など、なかなか理解しがたい点が多々ある。正太郎の生母・おたんは、庄屋の娘で正太朗の父親との恋の末、正太朗を産み落とすが、その後、親の命令で若い二人は引き裂かれ、女性のおたんの方は福井・武生の御用商人に嫁がせられて行ってしまう。正太朗の生母おたんに対する思慕の念や、ぜらのおたんに対する侮蔑の感情などについては、「女の手取川 第三部」で背景が明らかになる。
本書のタイトル「緋は紅よりも」については、本書のあとがきに、著者は以下のように述べている。”ヒロインの加賀屋七代は、きびしい風土にたえぬく女である。彼女を奮い立たせるもの、それは北陸の大自然であった。この「七代」を引き立てんがために、彼女の両極に「緋」と「紅」の女を配した。いうまでもなく、前者は姑ぜらで、後者は実母すまである。奔放でしたたかなぜらは、・・・・狂気めいているが実は正常という、いわゆるパラノイアの人で、北陸では異質の存在である。ぜらの緋とは、火の色、日論の色(中でも朝日を指す)を象徴する。”と書いている。本書の本文中にも、ぜらの心の声として、「雪国の女いうもんは、緋でなけりゃつとまりまへんのや。紅よりも強うなけや」とか「北陸のおなご言うもんは、雪の中の埋み火みたいなものですのや。大きな炎では芯まで燃えつき、小さな炎では雪に消されてしまう。自分を緋色に染めることや。緋とは火の色、日輪の色、朝日や。緋は夕陽の紅よりも、はるかに力強いんですのや・こうして雪以上に雪でなければ、北陸のおなごはつとまりまへん。・・」と記されている。
加賀屋七代としての加賀屋での嫁、妻、母としての暮らしぶりが、大河小説「女の手取川」第二部の本書の主題であり、加賀屋七代は、夫・加賀屋大海との間に、長女の竹子、次女の麻耶、第3子の長男・大彦の母となり、特に長女の竹子は、1943年(昭和18年)春の結婚の翌1944年(昭和19年)1月に誕生。母としての加賀屋七代の記述から、本書では、かなり、長女の加賀屋竹子からの幼少期から娘時代の視点・記憶に裏打ちされた生々しいエピソードが多くなっている。これは、本書は、著者・三田薫子 氏の母をモデルとした作品と言われるが、著者・三田薫子 氏自身も、七代の長女の竹子と同じく、1944年(昭和19年)美川町生まれ。尚、加賀屋七代は、第4子は、1956年(昭和31年)実弟・清の料理屋「華屋敷」の開店祝いの時に流産している。
本書では物語は、序に次いで全17章に分かれているが、最初の章「手取川の女たち」から、第7章にあたる「竹子誕生」までは、七代が同じ美川町に嫁ぐ昭和18年(1943年)から、戦時期・終戦直後の美川町の町や商家の様子が描かれる。海沿いの美川町らしく、戦時中の真夏に、塩田作りに浜に各家の女性たちが強制的に駆り出されていたり、敗戦直後の町に復員兵たちが職がなくうろうろする様子や美川の町野女性たちは精力的に浜に出て働いたことも書かれている。暮らしの中での土地の生活風習なども興味を惹くが、本書の終盤では、「女の手取川」第一部で子供時代の万屋七代が仲良かった弟の清が登場し、1956年(昭和3年)に、鎌倉、江戸、明治と全盛をきわめた、本吉港の名残をとどめる廓続きの手取川河口に、三階建檜造りの料理屋「華屋敷」を開店する。近くに、この地の産土神である藤塚神社、御薗座、芸者髪結屋、芸者風呂などがある南町界隈で、美川町出身の作家で大正文壇にその名を輝かしめた島田清次郎(1899年~1930年)の生家跡とは目と鼻の先。清の妻・華の実家は、吉原釜屋(現・能美市吉原釜屋町)だが、華の実家の分家に嫁いだのが、「女の手取川 第一部」に登場していた、島田清次郎の姻族で万屋の近所の床屋の娘・手取美代子で、彼女が清と華の仲人。
1948年(昭和23年)、アイヌのコタン(部落)の酋長の姪・リリカが、北海道から本州に向かう漁師に頼み込み、コタンから密かに船で福井まで南下し、電車で福井方面から美川に、七代の夫・加賀屋大海を訪ねてきた話には驚く。七代と結婚する前に、戦時中に満州で二人は出会い愛し合っていたという過去があった。アイヌの生活風習についての紹介が非常に詳しいが、美川とアイヌとの関連についての記述も興味ぶかい。美川の町に、平加というところがあったが、比楽加または平瓮(ひらか)とも言われ、平安期には、そこに手取の源流、比良河が走り、平加は比良湊のあった跡だとも、比楽駅の跡だとも言われている。ピラとはアイヌ語からきているという説もある、などとも紹介している。
本書で強烈な印象を残しているのは、加賀屋の左隣の唐傘屋の若い一人娘・町子の存在。「親族や近所、町などの柵、因習、そんなちっぽけなものと互いに数珠つなぎになっていて、そこで自分自身を見失うなんて・・・町子はイヤよ。皆、仲良くしてみせてるだけ。この町ではほどよく弱い人間だけが救われるのよ。強者も弱者もだめ」「この町の人々はね、自分たちで呪いの原因を作っておいて念仏で片付けようとする。だがら、毎日、嫁だ姑だ血族だ、なんて滅入るようなことばかりを言いつづけてるわ」などと言い切る町子は、家を畳み、老いた両親ともども、恋人のアメリカ人のもとにアメリカに飛び立っていく。そんな町子を、竹子は、北陸の鬱陶しい風景を切り裂いていく勇気がある人と誇らしく思う。
「女の手取川」第二部の本書も、第一部同様、美川町(旧・石川県石川郡美川町、現・石川県白山市美川地区)の旧町が本書ストーリーの主舞台ではあるが、美川町以外では、石川県金沢市湯涌(ゆわく)の湯涌温泉が、昭和18年(1943)春、加賀屋大海と七代の新婚旅行先として登場する。加賀屋大海が戦地で痔を患い、帰国してからその手術もしていたので、養生を兼ねて治療に効用のあるとされる湯湧温泉が選ばれた。金沢の奥座敷と言われる山里の秘湯の湯湧温泉は、奈良時代初期の養老年間の718年(養老2年)開湯と言われ、大正6年(1917)秋、大正時代を代表する詩人画家・竹久夢二(1884~1934)が愛人の笠井彦乃と6歳の次男の愛児・不二彦を連れて遊んだと言われる温泉で、七代たちの宿も、夢二たちが宿泊したのと同じ処。宿の名前は本書では明記がないが、これは、湯湧温泉の山下旅館(現在は、お宿やました)。竹久夢二と笠井彦乃は、大正6年(1917)8月~10月、北陸・加賀路を旅するが、9月下旬から10月の3週間が金沢の湯涌温泉滞在となった。加賀屋正太朗とぜら夫婦が、孫の竹子を連れてよく湯治にいくのが、手取川上流の中宮温泉(白山市中宮)。
目次
序
1. 手取川の女たち
2. 初夜
3. おぜらさま
4. おたんの梔子
5. 緋の女
6. 七代と菊
7. 竹子誕生
8. アイヌ娘
9. リリカの恋人
10.おかけの無花果
11.赤い靴
12.唐傘屋町子
13.きりえ
14.白いけものと夜
あとがき
<主なストーリー展開時代>
・1943年(昭和18年)春~1958年(昭和33年)1月
<主なストーリー展開場所>
・石川県(美川町、金沢、湯湧温泉、中宮温泉)
<主な登場人物>
・加賀屋七代(大正10年(1921年)美川町生まれ。生家は「万屋」)
・加賀屋ぜら(加賀屋の女主で七代の姑)
・加賀屋正太朗(加賀屋の当主で、ぜらの夫)
・加賀屋大海(七代の夫。加賀屋ぜらと正太朗の長男)
・万屋すま(七代の母。血縁続きの万屋の養女)
・万屋平作(七代の父で中風)
・万屋平次(七代の長兄で万屋の当主)
・加賀屋竹子(加賀屋七代と大海の長女で、昭和19年(1944)1月31日誕生)
・加賀屋麻耶(加賀屋七代と大海の二女で、昭和22年(1947)4月3日誕生)
・加賀屋大彦(おおひこ、加賀屋七代と大海の第三子)
・加賀屋海流(加賀屋ぜらと正太朗の次男。1943年秋に結婚し、美川町の新町に新世帯)
・加賀屋海陸(加賀屋ぜらと正太朗の三男)
・加賀屋海風(加賀屋ぜらと正太朗の四男。結婚後は分家して金沢で生活)
・菊(加賀屋海流の妻で金沢の米屋の娘。美川町の新町の新世帯入居)
・唐傘屋町子(加賀屋の左隣の傘屋の一人娘で金沢の旅行会社勤務、竹子より13歳年上)
・町子の両親(美川の大正通りの唐傘屋)
・かのえ(加賀屋海陸の妻。昭和27年(1952)32歳で病死)
・きりえ(加賀屋海陸とかのえの長女。32歳で白血病で病死)
・みい子(加賀屋海陸とかのえの末娘。母かのえ病死後、加賀屋海流・菊夫婦の養女)
・おたん(加賀屋正太朗の母)
・リリカ(アイヌの女性で加賀屋大海の元恋人。七代より7歳年下)
・万屋カラ(万屋平次の嫁で平木の郷の出身)
・野川(加賀屋の通いの雇い人)
・北山(加賀屋の通いの雇い人)
・一子(いちこ、七代の長姉、1914生まれで小松の呉服屋に嫁ぐ)
・清(七代の弟で、1947年、華と結婚。1956年に料理屋「華屋敷」開店)
・華(万屋清と結婚。吉原釜屋から美川町に嫁ぐ)
・八重垣(七代の末妹で、1947年、金沢の堂門家に嫁ぐ)
・万屋三郎(七代の次兄。1937年(昭和12年)5月、中国で戦死)
・美川町の日本舞踊の師匠で年増の芸妓(1954年、井戸に身を投げ自殺)
・美川町の日本舞踊の師匠で30歳女性(1954年、妾腹の子2人を残して海へ入水自殺)
・美川町の日本舞踊の師匠で町子の従姉(1954年、芸にいきづまり前途を儚んでの鉄道自殺)
・金沢にきて美川に寄った東京の歌舞伎役者
・アメリカ人のクラーク(町子の恋人)
・リリカの兄で、満州の某商社勤務
・M氏(満州の某商社の支店長。加賀屋大海と同郷人)
・おかけ婆さん(美川の山車屋敷近くの高浜の廃屋に住む、元格子女郎)
・加賀屋の真向かいの八百屋・美川屋の親爺
・ぜらの母親
・ぜらの9人の弟妹たち
・万屋の炊事場で働く雇われ女たち・湯湧温泉の宿の女将と女中
・美川町に一番近い橘村の在所の人
・島田清次郎(作家。1899年~1930年)
・手取美代子(島田清次郎の姻族で、1915年生まれの手取屋の床屋の娘)
・万屋春広(七代の次兄。父・平作の実家である広川家を継ぎ料理屋を営む)
・七代の末妹・八重垣の夫(金沢の堂門家)
・華屋敷開店の祝席でのひどく酔っ払った一人の酌婦