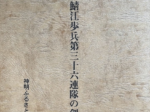- Home
- 南越地域の歴史事件・史跡・遺跡, 「南越」地域文化
- 南越地域の史跡・遺跡「享保水論殉難者之墓」と「水理碑」(福井県鯖江市落井町)
南越地域の史跡・遺跡「享保水論殉難者之墓」と「水理碑」(福井県鯖江市落井町)
南越地域の史跡・遺跡「享保水論殉難者之墓」と「水理碑」(福井県鯖江市落井町)
(写真下:正立寺(福井県鯖江市落井町)に建つ享保水論殉難者之墓<*2023年8月13日午後訪問撮影>


 (写真上:享保水論殉難者之墓が建つ正立寺(福井県鯖江市落井町)<*2023年8月13日午後訪問撮影>
(写真上:享保水論殉難者之墓が建つ正立寺(福井県鯖江市落井町)<*2023年8月13日午後訪問撮影>
享保水論殉難者之墓
享保13年(西暦1728)落井と下村との水論の犠牲者3名の墓なり
庄屋 太左ェ門 打首財産没収
長百姓 次郎衛 打首
次役 茂右ェ門 四十里外追放
落井を水難より救はんと争ひしに越前松平藩の裁きは我が主張を認め乍らも争ひを起せし事を咎め、責任者は重刑に処せらる部落民の犠牲となられし報謝の為明治初年落井村一同の懇念によりてこの墓が建てられしも年月を経るに従ひ荒廃せし故、此処に移転せり
昭和47(1972年)6月25日 落井相続講
太左ェ門 末裔 中林太右ェ門
茂右ェ門 末裔 渡辺治郎右ェ門
市誌調査委員 中林重松
(写真下:享保水論殉難者之墓の墓石3面 <*2023年8月13日午後訪問撮影>
 <墓石正面> 「法名 道専 墓 享保十三戌申年 六月廿五日 太左衛門」
<墓石正面> 「法名 道専 墓 享保十三戌申年 六月廿五日 太左衛門」
 <墓石向かって左側の面> 「法名 了祐 墓 享保十三戌申年 六月廿五日 次良衛」
<墓石向かって左側の面> 「法名 了祐 墓 享保十三戌申年 六月廿五日 次良衛」
 <墓石向かって右側の面> 「法名 正源 墓 寛政四壬子年 正月十六日 茂右衛門」*1790年
<墓石向かって右側の面> 「法名 正源 墓 寛政四壬子年 正月十六日 茂右衛門」*1790年
享保水論殉難者合祀の墓は、明治初年(1868)、落井村の村民により、落井正立寺(現・福井県鯖江市落井町)総墓の後ろに建立され、一つの墓石の3面に、殉難者3名の法名が刻まれている。しかし、そこは藪地で荒れ果て、余りにも粗末だというので、相続講の尽力で同寺境内の一角に移転。昭和47年(1972)6月25日、庄屋の太左ェ門末裔の中林家と次役茂右ェ門末裔の渡辺家の両家と相続講の共催で、244回忌法要が営まれ、その傍らに由緒を刻んだ14世住職孝正師の撰になる供養碑を建立。(庄屋の太左ェ門とともに、打ち首となった長百姓の次郎衛の家は絶家)
享保の水論(すいろん:水争い)
享保13年(1728年)、長年、水の便が悪くて困っていた松成・吉谷・四方谷の3集落が取水(水路・堰)の2つの計画を立て、落井へ申し入れてきた。一つは、集落の上の通称長太ヶ淵に取入口を設け、河和田川の水を引いて落井の集落の中心を縦貫する用水路の建設。もう一つは、落井、松成の境界付近でせき止めて灌漑に供する案。河和田川、鞍谷川の合流点(二タ口<ふたくち>近くに位置する、低い土地の落井にとって、応じられる案ではなく、松成、吉谷、四方谷の3集落は、落井の集落が容易に聞き入れないので、福井藩に訴願。
これに対して、落井では村中が寺に集まり協議の結果、落井の庄屋の太左衛門(60余歳)、長百姓の次郎衛(50余歳)、次役の茂右衛門(20余歳)の3人が福井藩に阻止陳情を行った。調査の結果、3集落の訴願を許可する方針に傾いた福井藩に対し、堰の構築には必死の阻止陳情することになり、別の鯖江藩領であった隣の川島の村も堤防決壊による田畑流失の恐れが出てくるものであり、次役は親類にあたる川島の庄屋太夫に相談。利害が重なる川島の集落にも堰構築の弊害を伝え、川島の人達は鯖江藩に利水工事の阻止陳情することになり、そのころ、別件で福井藩にいろいろと不満があった鯖江藩は、「領界で新たに水利工事を施工するならば、その許可と交換条件に、幕府拝領の門の再建と、北陸道をもとの通りに屈曲させること」wp福井藩に要求。その結果、福井藩は落井縦貫の用水路工事の事は自領内であるので許可したが、家屋浸水の恐れのある堰構築の工事は一応見合わせるということになり、落井の陳情は果たされたことになった。当時、福井藩主は第10代藩主・松平宗矩(まつだいら・むねのり、1715年~1749年)、鯖江藩主は2代藩主・間部詮方(まなべ・あきみち。1709年~1785年)。
しかし、5万石の鯖江の小藩に干渉されて面目を失った福井藩は「落井は福井藩でありながら、他藩と同腹して福井藩の計画を阻止した」として、庄屋、長(おさ)百姓、次役の3人を捕えて投獄。獄中の3人は、連日拷問にかけられたものの、いずれも屈せず、終始一貫申し立てを変えなかったという。
一方、庄屋、長百姓、次役のそれぞれの屋敷は、青竹の矢来を巡らされて外部との連絡を絶たれてしまう。
村人たちの奔走もむなしく、庄屋60歳代は打ち首・財産没収。長百姓50歳代は打ち首。次役20歳代は40里外追放・家族は土地払いという厳罰となる。京都へ流された次役は40年後、松成、吉谷、四方谷の3集落から、余りにも家が哀れなことになっているということで罪の願い下げの申請があり、帰宅を赦され、寛政4年(1792年)1月16日、90余歳で死去。次役の茂右衛門の妻は、打ち首となった次郎衛の娘。屋敷は青竹の矢来がめぐらされ家へ入ることが禁じられていたので乙坂今北村の道場に身を寄せた。毎朝必ず花を持ってわが家へ通い外から仏壇に向って礼拝して帰ったという。
落井ではその後、天保11年(1840年)6月24日25日の両日、太左衛門宅において3人の法要を営み、以来、水論講と称して村人全員が講員となり、打ち首になった2人の命日、6月25日の講日には、『水のお講さま』と呼んで、両家と講発起人で世話方である伊右衛門を招き、村民は飯を持って寺に参詣し犠牲者の霊を弔ってきたが、この法事も、第2次世界大戦中、食糧事情悪化に伴い途絶える。
長太ヶ淵を望む弁財天山の中腹に落井村が提供した一坪の墓地があり、ここに太左衛門と妻の墓がある。絶家となった次郎衛の墓は治左衛門の墓地に、茂右衛門の墓は末裔の治郎右衛門の墓地に祀られている。
水理碑 (福井県鯖江市落井町)
落井の村の西外れの河和田川沿いに建つ水理碑の石碑。長太ヶ淵から松成への用水路は、幕末に福井藩の奉行徳山五太夫によって改修され、幅約2mの完全なものとなり、明治36年(1903)頃、落井の古橋近くの用水路の橋が架け替えられた時、水路底から厚さ30cm、幅82cm、長さ145cmの石が発掘され、碑に適していると治郎右衛門から申し出があり、石碑が村人により建立された。明治の終わり頃に、村人により建立されたが、石碑は、その後、昭和33年(1958)の河和田川改修で、昭和52年(1977)の東陽中新設に伴う片上地区からの通学路整備により、そして平成18年(2006)には再び河和田川改修でと、場所を再三移転。
平成18年(2006)6月に建立した碑銘には、「享保13年(1728)におこった水論の犠牲者三人の霊を弔いその事蹟を後世に伝えるため明治末に村民の総意でこれを建立す」と記される。
(写真下:水理碑(福井県鯖江市落井町)<*2023年8月13日午後訪問撮影>


 水理碑の前面には、「水理碑」の文字が刻まれている。
水理碑の前面には、「水理碑」の文字が刻まれている。
 水理碑の背面には、右より以下と刻まれている
水理碑の背面には、右より以下と刻まれている
享保十三戌申年六月二十五日
(右に) 了 祐(長百姓、次良衛)
(中央に)釈道専(庄屋、太左ェ門)
(左に) 正 源(次役、茂右ェ門)
中河村原 石工 酒井甚左ェ門
 (写真上:水理碑は河和田川沿いに建ち、この写真の左側の川沿いに水理碑がある)
(写真上:水理碑は河和田川沿いに建ち、この写真の左側の川沿いに水理碑がある)
参照:「北中山の歴史・伝承(語り部教本)」(北中山語り部の会、2020年3月発行)、「北中山の歴史・伝承(第2教本)」(北中山語り部の会、2023年3月発行)