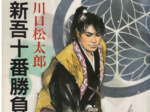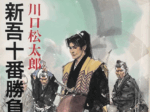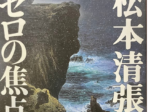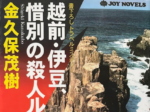- Home
- 北陸地域関連書籍, 「越」関連書籍紹介, 北陸を舞台とする小説
- 北陸を舞台とする小説 第26回 「蛍川」(宮本 輝 著、筑摩書房)
北陸を舞台とする小説 第26回 「蛍川」(宮本 輝 著、筑摩書房)
北陸を舞台とする小説 第26回 「蛍川」(宮本 輝 著、筑摩書房)
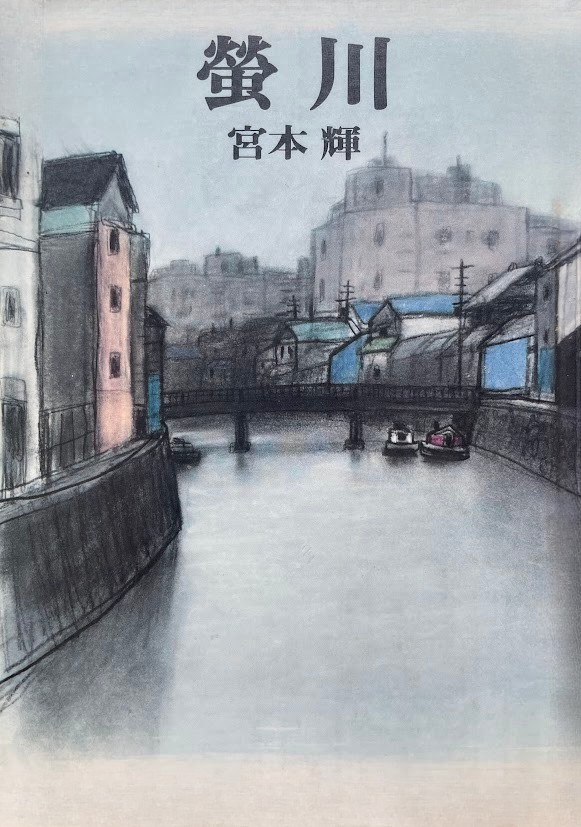
<単行本>「蛍川」(宮本 輝 著、筑摩書房、1978年2月発行)

<文庫本>「蛍川」(宮本 輝 著、角川文庫、1980年2月発行、改版2018年10月発行)
宮本 輝(みやもと・てる)<文庫本の著者紹介より、文庫本改版発刊当時>
1947年兵庫県神戸市生まれ。追手門学院大学文学部卒。1977年「泥の河」で太宰治賞、1978年「蛍川」で芥川賞、1987年「優駿」で吉川英治文学賞、2004年「約束の冬」で芸術選奨文部科学大臣賞文学部門、2010年「骸骨ビルの庭」で司馬遼太郎賞を受賞。同年紫綬褒章受章。
「蛍川」は、1977年「泥の河」で第13回太宰治賞を受賞して30歳で作家デビューした宮本輝(1947年~ )の小説で、1978年1月18日に、第78回芥川賞を受賞した作品。「泥の河」は、1977年7月『文芸展望』18号に初出掲載で、「蛍川」は、同じ年の続く1977年10月『文芸展望』19号に初出掲載。筑摩書房の単行本「蛍川」は、「蛍川」に「泥の河」を併録して、1978年2月に発行された。
「泥の河」は、戦後10年の昭和30年(1955年)大阪安治川河口でうどん屋を営む父母(晋平・貞子)と暮らす8歳の小学2年の少年・板倉信雄が主人公だったが、「蛍川」は、昭和37年(1962年)3月末から同年初夏にかけて、富山市豊川町に父母(重竜・千代)と暮らす中学2年から中学3年に進級する少年・水島竜夫が主人公。泥の河」と「蛍川」は、別々の物語ながら、主人公の少年が、共に昭和22年(1947年)生まれと推定でき、昭和22年(1947年)生まれの著者と同年代という設定。「泥の河」「蛍川」に、1981年発表の「道頓堀川」が、宮本輝の川三部作として挙げられ、3作品とも映画化されている。
「蛍川」は、富山市豊川町に両親と暮らす主人公の少年・水島竜夫が、中学2年生の終わりの1962年(昭和37年)3月末から、中学3年生に進級し同年の初夏までの主に富山市を舞台とする物語。小学校4年生になった5年前、4月に大雪が降ったら、その年こそ田植えの前の時期に、富山市街地を流れる、いたち川の上流に、ものすごい数の蛍の群れを見に行こうと、八人町(富山市八人町)に仕事のある建具師の銀蔵爺さんと約束をしていたが、中学3年に進級した年の4月に大雪が降り、水島竜夫は、ほのかに思いを寄せる幼馴染の同級の辻沢英子にも、蛍の大群を一緒に見に行こうと誘う。幼馴染の英子とは、小学生の頃はよく一緒に遊んだものだったが、中学に入った途端、急に口もきかなくなっていた。
この短い期間の物語の展開は、まず、水島竜夫の父・重竜が、富山市の自宅で脳溢血で倒れる。父親の水島重竜は、戦後の復興時、進駐軍の払下げである古タイヤの大量販売によって大金を掴むと、それに関連した自動車の部品にまで手を伸ばし、北陸では有数の商人にのしあがり、勢いに乗って次々と新しい事業に手を染めていったが、昭和28年(1953年)頃を境に取り組む事業のことごとくが行き詰り、1年前に事業が倒産、多くの借金を抱えていた。水島重竜には、妻・春枝がいたが、春枝との間には子供ができず、戦後の1947年初に金沢で、千代と出会い、千代の間に子供ができ、水島重竜は、20年連れ添った春枝と別れて、千代と再婚し、千代と2人で、富山市豊川町の家に移り、52歳になって、一人息子の竜夫が生まれていた。
水島竜夫の45歳の母親・千代は、夫の重竜が脳溢血で倒れてから、これからいったいどうやって生活していこうか、借金だらけで、そのうえ、収入の道は閉ざされていて、自分が働く以外に道はないのだが、生活費に夫の入院費などがかさみ、途方にくれることになる。千代は、21歳で田畑持ちの裕福な家の長男で鉄道員の夫を結婚するが、すぐに別れ、結核で寝たきりの母が兄と二人で住んでいた富山県射水郡小杉町(2005年に射水市に新設合併)の実家に戻る。父は千代が子供の時に亡くなり、千代の兄には召集令状が届き、母親は戦争が終わって一年目に亡くなり、千代は、金沢の「田村」という料亭で、女主人の補佐として勤めるようになる。そこで、戦争が終わって3年目に入ろうとする頃、当時、北陸道でにわかに名をしられ始めた水島重竜と知り合う。
中学3年になった水島竜夫は、辻沢英子が大好きと公言する級友の仕立屋の息子・関根圭太から、辻沢英子の写真を貰い、神通川に魚釣りに誘われるが、父の見舞いに病院に行かねばならず、一人で出かけた関根圭太は神通川で溺れ死ぬ。それから間もなくして、父・重竜も病院で息を引き取り、親友と父の死に立て続けに遭い、母・千代は、大阪で飲食店を経営し店舗を拡大予定の千代の兄・喜三郎から、竜夫を連れて大阪に移り住むことを持ちかけられ、思い悩むことになる。父親や級友の死に遭い、母親の苦悩を感じ、幼馴染にほのかな恋心を抱く思春期の少年・達夫の姿や、達夫の目に映る大人の世界が、詩情豊かに描かれ、美しい文章が溢れる作品。ラストシーンの蛍の大群の描写も圧巻だが、富山の街の雪や川の描写も美しい。
特に父親の無念さや事業運に見放された気弱さ、遅くにできた一人息子の成長を気にかけ、妻子の将来を心配する、以前は豪放な事業家だったはずの父・水島重竜の姿が非常に切ない。水島竜夫の辻沢英子を想う思春期の様子や、「英子は、ええ匂いがするがや。熱情的やのオ、英子のフェロモンは、熱情的やのオ」と話す級友の関根圭太の直情的な思春期の少年の姿も懐かしい。他にも、金沢で旅館業を営む重竜の先妻の春枝が、重竜が亡くなった直後に富山市に千代を訪ねてきた時の竜夫を慈しみ一緒に金沢に帰る途中の高岡まで竜夫が同行する場面で、「おばちゃんのできることは何でもしてあげるちゃ。商売が何ね、お金が何ね。そんなもんが何ね。みんなあんたにあげてもええちゃ・・」と涙声で語る春枝の心情や、父・重竜の古くからの友人で高岡市に住む大森亀太郎に母の依頼で竜夫がお金を借りにいくシーンでの、大森亀太郎の応対ぶりもなかなか染みる場面。更に、15年前の冬に、出会ったばかりの水島重竜と千代が、福井市の旅館に泊まり、冬の越前岬を訪ねる場面も名場面。
主人公の少年・水島竜夫が父母と暮らす家は、神通川と常願寺川をつなぐ富山市街地を蛇行しながら流れる、いたち川が家の前を流れる、豊川町(富山市豊川町)にある設定で、豊川町以外にも、銀蔵爺さんの仕事場がある八人町(富山市八人町)や、母と出かける繁華街の西町(富山市西町)、富山城の公園でのサーカス見物など、富山市街地が主な舞台で、富山の市街地を走る市電のシーンも度々登場する。著者の宮本輝 氏 自身は、1947年(昭和22年)3月に。自動車部品を扱う事業を手掛けていた宮本熊市の長男として、神戸市に生まれるが、その後、幼少期には、愛媛県、大阪府、富山県に転居している。小学校は大阪市立曽根崎小学校に入学したが、1956年(昭和31年)に、父の事業のため富山市豊川町に転居し、富山市立八人町小学校に転入している。ただ、翌1957年(昭和32年)に、父親の事業が失敗したために、兵庫県尼崎市に転居し、尼崎市立難波小学校に転入している。「蛍川」は、1987年2月公開で映画化されているが、映画「蛍川」のロケモニュメントが、いたち川の清辰橋の手前(富山市辰巳町)に建立されている。
目次
泥の河
蛍川
<主なストーリー展開時代>
・1962年(昭和37年)3月末~初夏
<主なストーリー展開場所>
・富山県(富山市・高岡市)
・<15年前の冬の回想>福井県(福井市内、越前岬)、石川県(金沢、大聖寺)
<主な登場人物>
・水島竜夫(中学2年から中学3年に進級する)
・水島千代(竜夫の母で45歳)
・水島重竜(しげたつ、竜夫の父)
・辻沢英子(辻沢歯科の娘で、竜夫の幼馴染)
・関根圭太(竜夫の級友で、2年前に母親を病気で亡くし父一人子一人の生活)
・関根圭太の父(洋服の仕立屋)
・春枝(重竜の先妻で63歳、金沢市内で旅館業を営む)
・銀蔵(八人町に仕事場がある75歳の建具師。妻に先立たれ娘夫婦と暮らす)
・大森亀太郎(高岡市に住む父の友人で、大森商会の代表)
・喜三郎(千代の兄で、大阪で飲食店を経営)
・辻沢初子(辻沢英子の母)
・病院の医者
・市電の中の魚行商の老婆
・市電のレール脇に立つ作業員
・市電の若い車掌
・富山城で誰かを待っているらしい30前後の和服の女性
・竜夫の近所に住む級友の少年
・竜夫の同じクラスの女生徒
・竜夫のクラスの教師
・竜夫の通う中学校の用務員
・重竜が入院する病院の中年の看護婦
・百合っぺ(竜夫の近所の女の子で小学2年の時の遊び相手)
・千代の別れた夫(鉄道員で、田畑持ちの裕福な家の長男)
・千代と先夫との間の子
・千代の別れた夫の舅と姑
・福井市内の宿の番頭
・三味線弾きの50近い小柄の盲目の女
・源二(銀蔵の息子で大工。建築中の家の屋根から落ちて亡くなる)
・源二の許婚(礪波の石屋の娘)