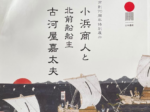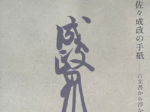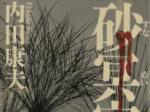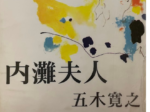- Home
- 北陸地域関連書籍, 「越」関連書籍紹介, 北陸を舞台とする小説
- 北陸を舞台とする小説 第21回 「新吾十番勝負(中)」(川口 松太郎 著)
北陸を舞台とする小説 第21回 「新吾十番勝負(中)」(川口 松太郎 著)
北陸を舞台とする小説 第21回 「新吾十番勝負(中)」(川口 松太郎 著)
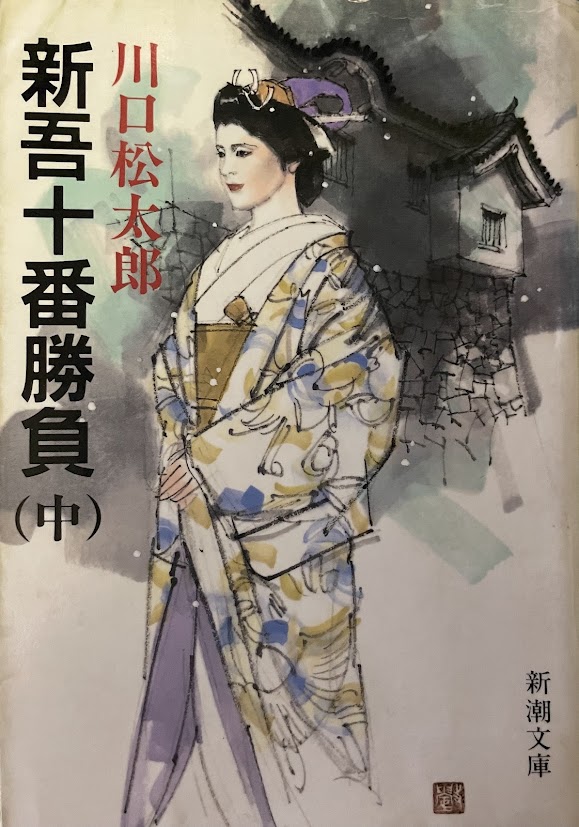
「新吾十番勝負(中)」(川口 松太郎 著、新潮文庫<新潮社>、1965年6月発行)
<著者略歴> 川口 松太郎(1899年~1985年)
(*他著作での著者略歴をベースに編集。本書には著者略歴記載なし)
1899年(明治32年)東京・浅草生まれ。若くして久保田万太郎に師事、のち講談師悟道軒円玉に江戸文芸・漢詩を学ぶ。1923年(大正12年)、小山内薫の主宰する「劇と評論」に脚本『足袋』を発表。同年、大阪で直木三十五らと雑誌「苦楽」を編集。その後大衆作家を志し、1934年(昭和9年)に「鶴八鶴次郎」を発表。菊地寛に激賞される。翌年「風流深川唄」を発表、第1回直木賞を受賞する。その後、「愛染かつら」で人気作家になる。芸道小説、時代小説、風俗小説に独自の話術をもって庶民的心情をとらえる。昭和15年(1940年)劇団新生新派の主事を務め、以後新派の育成に力を注ぎ、戦後は大映映画の重役をつとめ、映画、演劇の製作にも活躍した。菊地寛賞、吉川英治文学賞など受賞歴多数。脚本多数執筆。1966年芸術院会員となり、1973年文化功労者となる。
本書「新吾十番勝負」の著者は、東京市浅草区生まれの昭和を代表する小説家・劇作家の川口松太郎(1899年~1985年)で、実の両親を知らない川口松太郎 氏は、早くから自立心旺盛で小学校を卒業すると様々な職業を転々とした後、久保田万太郎に師事した後、大衆作家を目指し「鶴八鶴次郎」などで第一回直木賞を受賞。代表作に「風流深川唄」「明治一代女」「愛染かつら」など多数の著作があり、脚本・シナリオも多く、映画演劇界の大御所的存在。数多くの時代小説も書き、本作「新吾十番勝負」は代表作の一つ。「新吾十番勝負」は、1957年(昭和32年)5月から1959年(昭和34年)にかけて、朝日新聞に700回以上、約2年間にわたり連載された痛快時代小説で、八代将軍徳川吉宗の御落胤・葵新吾の剣の道を描く大長編で、映画化・テレビドラマ化も度々行われた人気作品。
単行本は、「新吾十番勝負(美女丸の巻)」(新潮社、1957年12月発行)から、「新吾十番勝負(お鯉の巻)」「新吾十番勝負(流離の巻)」「新吾十番勝負」(剣聖の巻)と、全4巻シリーズで最初に刊行。その後、新潮文庫から、上中下3巻セットから文庫版が出版され、更に「新吾十番勝負」については、その後も、嶋中書店(嶋中文庫)から2005年・2006年に、全5巻シリーズで文庫セット、捕物出版よりは、2023年に4巻セットで復刊されている。1957年(昭和32年)5月から1959年(昭和34年)にかけて朝日新聞に長期連載された「新吾十番勝負」は大変好評で、その後、産経新聞に「新吾二十番勝負」「新吾番外勝負」が連載され、シリーズ化となり、これらの「新吾二十番勝負」「新吾番外勝負」についても、書籍出版や映画化・テレビドラマ化が行われた。書籍「新吾十番勝負」については、「美女丸誕生」と「第一番」から「第十番」までの計11章から成り、新潮文庫本3セットでは、中巻では、「第四番」から「第七番」までを収めている。
⇒書籍紹介「新吾十番勝負(上)」(川口 松太郎 著、新潮文庫<新潮社>
「第四番」では葵新吾は、秩父から鹿島(現・茨城県鹿嶋市)に出かけ、江戸にちょっと戻る事にはなるが、他の章と違って、この「第四番」では、諸国歴訪で各地を巡るということなく、物語の舞台は、殆どが鹿島(現・茨城県鹿嶋市)と周辺エリア。「第三番」の終盤では、享保9年(1724年)6月、葵新吾が伊予国西条藩お預けを解除され、翌7月、秩父へ戻る途中に、三河岡崎で東海の大盗賊・浜島庄兵衛一党の話を再度聞くことになり、秋葉山や天竜川付近で一旦寄り道をすることになるが、享保9年(1724年)8月には、梅井多門、真崎庄三郎とともに葵新吾は秩父に帰り着いた場面から、「第四番」が始まる。鹿島の佐吉親分率いる鹿島の佐吉一門40人の博徒たちが、自源流を学びたいと、武州秩父の大台ケ原の自源流道場に登ってきて交流を持ったことから、鹿島神宮警固役をめぐる縄張り争いとも関わりを持ち関東博徒たちの世界を覗くことになる。享保10年(1725年)3月、鹿島神宮の春の大祭での将軍御代参を、将軍側室で葵新吾の生母・お鯉の方が務めることとなり、鹿島神宮で母子対面が実現するかどうかも「第四番」の見どころの一つ。
「第四番」では、鹿島(現・茨城県鹿嶋市)で、関東博徒の鉾田の虎吉親分だけでなく、悪代官の関東郡代次席・下島甚右衛門を、葵新吾は斬ることになるが、鹿島神宮・鹿島神宮門前町だけでなく、鹿島の周辺の水郷エリアが登場するのも旅情に満ち楽しい。葵新吾は、2か月あまり秩父に滞在しただけで、享保9年(1724年)10月には秩父の山を下り、利根川を船で下り、佐原(現・千葉県香取市)、牛堀(現・茨城県潮来市)を通り、水郷の風景を眺めながら、鹿島の町に到着するが、鹿島の町に到着後も、鹿島神宮の船着場で北浦の水辺の大船津(現・茨城県鹿嶋市)や霞ケ浦の浮島(現・茨城県稲敷市)、牛掘(現・茨城県潮来市)など近辺エリアにも物語が広がる。美男子剣士の葵新吾が、最初に女性経験をするという事でも、「新吾十番勝負」の中で「第四番」は特筆すべき。相手は、大名の姫とかではなく、ばくち打ちの鹿島の佐吉が潮来の酌取り女に生ませた妾の子・咲。葵新吾のお咲を好きになる眼差しが優しくもあり、「第四番」の最後の荒場が終わり、葵新吾が鹿島を去る際のお咲の家族に対する粋なはからいには、誰もが葵新吾をますます好きになってしまうはずだ。
「第五番」では、葵新吾と梅井多門・真崎庄三郎一行が、鹿島(現・茨城県鹿嶋市)から秩父に戻る途中で、上総の利根川沿いの小見川(現・千葉県香取市)の渡し場で、かつて大阪の豪商ながら20年以前の元禄期に没落し謀判の罪で家財没収に処せられていた淀屋の手代・要助が、岡村左平太という浪人風の武士に殺されそうになっているのを助ける場面からスタート。葵新吾一行は、上総の小見川から香取、滑川(現・千葉県成田市)、安孫子、野田、岩槻、川越を経て、享保10年(1725年)3月、秩父に戻るが、奈良の主人の元に戻る予定の要助は、小見川で出会った葵新吾一行とは、関宿(現・千葉県野田市)で別れ、武州戸田河原の渡し場(現・埼玉県戸田市)で、先回りしていた岡村佐平太に斬られてしまうが、偶々居合わせた放生一真流の武田一真に、言伝を頼み息絶える。要助の死ぬ間際の頼みで、武田一真は秩父の自源流道場を訪ねるが、剣の宿敵同士の梅井多門と武田一真は秩父の山中で勝負をするが、梅井多門は敗れ、翌年の3月15日、近江・比叡山で再勝負を二人は約するが、敗れた梅井多門は失明する。
失明した梅井多門の治療のために、葵新吾は真崎庄三郎とともに江戸・四谷の名医・安井東庵の診察を受けるが、大阪の名医・東谷良順の診察を勧められ、大阪では東谷良順から、淀屋のオランダ渡りの秘薬があればと言われて、奈良の淀屋を急ぎ訪ねることになる。こうして「第五番」の後半の主たる舞台は奈良と大阪に移る。奈良では、淀屋辰五郎の娘・須栄(すえ)と出会うが、須栄は「第五番」以降も葵新吾と深い関係になっていく。葵新吾は、大阪では、大阪城内の牢屋敷での水責めで密殺されそうになるが、危機を脱し元淀屋の手代で大阪有数の薬種商に成長した奈良屋勝三郎の不正を暴き、また淀屋を取り潰し更に苦境に追い込んでいた大阪城代・黒田備前守や大阪城代加番役・土方河内守とその義弟の大阪城代役人の岡村左平太の悪だくみを潰していく。取り戻した神君家康の朱印状をもとに、淀屋の旧領回復のため。享保10年(1725年)6月、葵新吾は、梅井多門、真崎庄三郎とともに、江戸に向けて大阪城を出立するところで「第五番」が閉じる。江戸入りには、旧領回復のために、淀屋辰五郎と須栄も同行するだけでなく、悪人の岡村左平太の剣のレベルを惜しみ岡村悪源太と改名させ、葵新吾の供侍として付き添わせていく。
「第六番」の物語は、享保10年(1725年)6月、淀屋の旧領回復のために葵新吾一行は江戸入りしたところからスタート。葵新吾は、初めて自ら大奥のお鯉の方にお願いしたいことがあると連絡をとるが、目的の淀屋の旧領回復の件は、久世大和守と松平伊豆守の2人の老中の反対に遭い、その事で、葵新吾は、鎌倉河岸(現・東京都千代田区内神田)と西丸下(現・皇居外苑)にある二人の老中それぞれの江戸屋敷に、単身で夜陰に紛れて忍び入り老中の左手を打ち脅かしてしまう。そして、2人の老中への狼藉のとがで、吉宗と紀州藩主・徳川宗直の合議で、葵新吾の紀州幽閉が決まる。なので、「第六番」の主な舞台は、紀州入りした享保10年(1725年)7月から、比叡山での梅井多門と宿敵・武田一真の対決のために密かに幽閉の紀州領を一時抜け出す享保11年(1726年)3月までは紀州領内。梅田多門と真崎庄三郎は江戸から秩父に戻り、葵新吾の紀州入りには岡村悪源太と須栄が付くが、和歌山城到着後、葵新吾は、早速、紀州家の柳生流師範代の穴沢市重郎から立ち合いを要望されるが、葵新吾に従う岡村悪源太が代わりに立ち合いの相手をし、勝ってしまう。このことが、柳生流の面子もあり、「第六番」の最後では、葵新吾が比叡山から紀州に向かう途中で京都所司代屋敷に連行された後、和歌山に戻り、和歌山城で紀州家の剣道指南番で柳生流七剣士の一人である宗田豊之進と対決をすることに至る。
紀州藩幽閉の身の葵新吾は、柳生流との模範試合を避けようとして和歌山城内を立ち去り、岡村悪源太・須栄と共に、和歌の浦を眺め、紀州街道を南に下り、那智の滝(現・和歌山県那智郡勝浦町)、勝浦町、串本と紀州領内を巡り、印南町から紀州道成寺(現・和歌山県日高郡日高川町)を訪問。享保10年(1725年)8月の立秋の夜には、奈良の淀屋辰五郎の娘・須栄と、道成寺門前の真如院という松寺に泊まり、そこで、葵新吾にとり人生2度目(初体験の相手は鹿島の佐吉の娘のお咲)となる女性との一夜を過ごす事になる。和歌山の紀州家では、葵新吾を求める捜索隊が紀州領内八方を飛び回るが、葵新吾一行は、道成寺塔中の徳願寺を改装し宿舎としながら、紀州幽閉の時を待っていた。松平伊豆守に代表されるように、徳川家に禍根を残さないために葵新吾を排除する陰謀を巡らす一派が幕閣にあり、葵新吾に反感を持つ紀州家国家老が柳生流一門を押し出し結託する動きと共に、「第六番」のもう一つのハイライトは、享保11年(1726年)3月の比叡山四明嶽での梅井多門と宿敵・武田一真の対決。葵新吾は、この比叡山での恩師の対決のために、密かに幽閉の紀州領を一時抜け出すが、梅井多門の敗死後、葵新吾は、真崎庄三郎から、急がないので、多門先生の毛髪を、越前鯖江の誠照寺へ届け、遺髪を寺へ届けて境内に墓所を作りたいと、依頼されている。
「第七番」のスタートは、享保11年(1726年)4月。和歌山城での葵新吾との勝負に負けた紀州家の剣道指南番で柳生流七剣士の一人である宗田豊之進が自害したことから、葵新吾を亡き者にしようとする老中松平伊豆守らの陰謀はいつしか世評の表面にものぼり、葵新吾に同情を持つ新任老中の酒井讃岐守をはじめとする幕閣たちによる、葵新吾の紀州藩幽閉を問題とする意見が強まり始める。結果、松平伊豆守は登城差し止め、久世大和守は退任となり、享保11年(1726年)6月末、葵新吾は紀州幽閉が解かれ、同年7月初には、江戸での将軍公式対面に向けて、江戸幕府からの迎えの使者とともに、和歌山を出発。「第七番」冒頭から新しく登場する新任老中の酒井讃岐守は、若州小浜(現・福井県小浜市)12万石の大名で、今後も酒井家は葵新吾の力になっていく。享保11年(1726年)7月、和歌山から江戸に向かう葵新吾の行列は、東海道の三島宿を越えた箱根山中で、お世継ぎの徳川家重お付きの若年寄・太田備中守の意向を受けた腹心の射撃の名手から狙撃を受け、その混乱を幸いに、もともと江戸行きを望んでいなかった葵新吾は、警固の行列から単身で逃げ切る。
その後、大道武芸の藤井一門と一緒に2か月、大道武芸を続けながら各地を旅し駿河路から遠州路に入るが、遠州浜松城下近くで、縄手の八五郎一家と天神の丑松一家との博徒一家同士の縄張り争いの助っ人に加わり相手方の助っ人に、恩師・梅井多門の宿敵だった武田一真を見つけるが、藤井一門の仲間たちは武田一真に殺されてしまう。武田一真をつけ狙う葵新吾とは立ち会いたくない武田一真の思惑通り、葵新吾は、浜松の諏訪明神へ誘い出され、老中松平伊豆守が藩主の浜松藩に引き渡されてしまう。葵新吾を亡き者にしたいものの浜松藩領内での表立っての実行は難しく、葵新吾を仇と狙う柳生流の宗田豊之進の遺児たちと柳生流首席師範の多羅尾平八に、浜松藩領外の遠州新居関所を越えた山道で待ち伏せさせ襲わせる。そこに、美濃国加納の安藤家の者たちが葵新吾を救い、近くで待機していた加納藩主・安藤対馬守の長女・綾姫と共に、遠州から三河に入るが、三河吉田藩城下を避け、享保11年(1726年)12月、三州御油のはたご屋に宿泊。ここで、ついに、葵新吾は綾姫と結ばれるが、これが葵新吾にとって3人目の女性。この日の夜の2人の会話のやり取りがなかなか痺れる。
こうして享保11年(1726年)12月には葵新吾は美濃国加納城に到着し、年をまたぎ、加納城で、しばらく平穏な日々を綾姫と過ごすが、享保12年(1726年)1月、浜松藩から好条件で葵新吾を討つ話を持ち込まれた武田一真は、浜松藩国家老・吉田次左衛門腹心の青年武士5人と共に、浜松から美濃国加納城下に入り、葵新吾を上手く外に誘い出し襲撃する。浜松藩武士の目つぶしにより葵新吾は絶体絶命の危機に陥ってしまうが、命は奪われずに、心配した加納藩士たちに加納城に連れ帰るが、悔しい思いをした葵新吾は、早く秩父の道場に戻り再修業をしたくて、享保12年(1726年)2月、加納城を抜け出すところで、「第七番」が閉じる。
「第七番」では、駿河・遠州・三河の東海道各地で、いろんな出来事が起こり、気になる地名や場所などが登場。「第三番」でも、東海道各地が主たる舞台となっているが、「第七番」では、浜名湖周辺の舞阪・新居は再登場ながら、初めて物語の舞台として登場する地名も少なくない。三島と小田原箱根口区間の箱根八里や三島宿・三島大社(現・静岡県三島市)、土狩村(とがり)(現・静岡県長泉町)、浜松城・諏訪神社(現・静岡県浜松市)、縄手・天神・中田村(現・静岡県浜松市)の地区、舞阪宿(現・静岡県浜松市)と浜名湖を挟んでの新居関所・新居宿(現・静岡県湖西市)など駿河・遠州領内もいろいろ登場するが、「第七番」では、やはり三河領の三河吉田藩と吉田城(現・愛知県豊橋市)、更には葵新吾と綾姫が一夜を共にした三州御油(ごゆ)の町が注目すべき場所。御油宿は東海道53次の35番目の宿場で、現在の愛知県豊川市御油町。「第七番」では、「第二番」に引き続き、美濃国加納藩の加納城下(現・岐阜県岐阜市)が物語の舞台として再登場するが、加納城下の南に川魚料理を食べに行ったエリアがどのあたりかも非常に気になるところ。
「新吾十番勝負(中)」(新潮文庫)目次
第四番
第五番
第六番
第七番
<主なストーリー展開時代>
・【第四番】享保9年(1724年)8月~享保10年(1725年)3月
・【第五番】享保10年(1725年)3月~享保10年(1725年)6月
・【第六番】享保10年(1725年)6月~享保11年(1726年)4月
・【第七番】享保11年(1726年)6月~享保12年(1727年)2月
<主なストーリー展開場所>
・【第四番】:秩父、江戸、鹿島及び周辺
・【第五番】:上総の小見川、関宿、戸田の渡し、秩父、江戸、大阪、奈良
・【第六番】:江戸、和歌山、紀州領内、近江坂本、比叡山、京都、(秩父)
・【第七番】:和歌山、大阪、三島、箱根峠,遠州浜松、新居、三州御油、名古屋、美濃国加納
<主な登場人物>
【第四番】
・葵新吾(越前鯖江藩主時代の徳川吉宗の落胤で長子)
・梅井多門(武州秩父の大台ケ原の自源流師範代で越前鯖江の誠照寺出身)
・真崎庄三郎(江戸神田九段下の自源流道場を任されている元鯖江の薬行商人)
・真崎備前守(武州秩父の大台ケ原の自源流流主)
・鹿島の佐吉(常州笠間の生まれの渡世人で、鹿島神宮警備の町人。渡世人の佐吉一門の親分)
・繁蔵(鹿島の佐吉の子分)
・伊奈半左衛門(関東郡代代官)
・下島甚右衛門(関東郡代次席代官。鉾田の虎松の妹を妾にしている)
・鉾田の虎松(鹿島の佐吉一門と敵対する渡世人の虎松一門の親分)
・お縫(将軍側室お鯉付きの大奥女中で、秩父八幡の宮司・一宮篤方の娘)
・お鯉の方(徳川吉宗の側室で葵新吾の生母。元は、越前鯖江の町人の娘・お長)
・徳川吉宗(江戸幕府第8代将軍、元・越前鯖江藩3万石藩主の松平頼方)
・一宮篤方(秩父八幡の宮司で、大奥のお鯉の方付きの女中・お縫の父)
・お縫の母
・彦十郎(鉾田一家の若親分で、虎松の腹違いの弟。鉾田一家の代貸を勤める)
・お咲(鹿島の佐吉の娘で妾の子。元鹿島神宮の巫女)
・おきん(潮来の酌取り女。佐吉の妾でお咲の母)
・桐生の松五郎親分(関東博徒)
・結城の新兵衛(関東博徒)
・野田の孫右衛門親分(関東博徒)
・辻六郎(下島甚右衛門の下役で、鹿島出役代官の臨時代理)
・本多伊予守(江戸幕府寺社奉行)
・浮島の八五郎(鹿島の佐吉の兄弟分で、霞ケ浦の網元のま魔の渡世人親分)
・松平左京頼安(徳川一門の伊予国西条藩3万石藩主。紀州宰相頼宜の孫)
・中山香庵(江戸城御典医)
・堀 山城守(江戸城奥御用人)
・大船津の船津屋の主人
・駒木根肥後守(江戸幕府大目付)
・藤七(鹿島の佐吉一門)
【第五番】
・葵新吾(越前鯖江藩主時代の徳川吉宗の落胤で長子)
・梅井多門(武州秩父の大台ケ原の自源流師範代で越前鯖江の誠照寺出身)
・真崎庄三郎(江戸神田九段下の自源流道場を任されている元鯖江の薬行商人)
・真崎備前守(武州秩父の大台ケ原の自源流流主)
・要助(奈良の油坂に住む淀屋辰五郎の手代)
・岡村左平太(大阪城代番士上りの城代役人)
・武田一真(放生一真流流主の浪人剣士)
・お縫(将軍側室お鯉付きの大奥女中で、秩父八幡の宮司・一宮篤方の娘)
・お鯉の方(徳川吉宗の側室で葵新吾の生母。元は、越前鯖江の町人の娘・お長)
・徳川吉宗(江戸幕府第8代将軍、元・越前鯖江藩3万石藩主の松平頼方)
・一宮篤方(秩父八幡の宮司で、大奥のお鯉の方付きの女中・お縫の父)
・お縫の母
・安井東庵(江戸・四谷の左内坂の名医)
・東谷良順(蘭人より医学を学んだ大阪の名医)
・当代(3代目)淀屋辰五郎(奈良の油坂在住)
・吾妻(淀屋辰五郎の43歳の妻で、元は大阪の新町遊郭の遊女)
・須栄(すえ)(淀屋辰五郎の20歳の娘)
・岡本三郎右衛門(淀屋の先祖で、大阪夏の陣での功績に徳川家康から恩賞をもらった材木商)
・(2代目)岡本三郎右衛門
・奈良屋勝三郎(大阪・道修町に店を持つ大阪有数の薬種商で、元は淀屋の手代)
・政五郎(大阪・順慶町のカゴ政というならず者)
・松平左京頼安(徳川一門の伊予国西条藩3万石藩主。紀州宰相頼宜の孫)
・坂本修理(大阪城代目付役人で、交代旗本坂本主計の3男で甲府御城代勤務より大阪表へ転勤)
・黒田備前守(大阪城代。黒田藩の末流の大名)
・土方河内守(大阪城代加番役で岡村佐平太の義兄)
・孝右衛門・天王寺屋五兵衛・小西源右衛門(元淀屋の大番頭)
・松平遠江守(尼ケ崎の大名で、病没後、12歳の少年・亀三郎が相続)
・佐々木勇斎(大阪市内ただ一軒の手裏剣鍛冶で、用賀流の忍術師)
・きく(佐々木勇斎の末娘)
【第六番】
・葵新吾(越前鯖江藩主時代の徳川吉宗の落胤で長子)
・梅井多門(武州秩父の大台ケ原の自源流師範代で越前鯖江の誠照寺出身)
・真崎庄三郎(江戸神田九段下の自源流道場を任されている元鯖江の薬行商人)
・真崎備前守(武州秩父の大台ケ原の自源流流主)
・お縫(将軍側室お鯉付きの大奥女中で、秩父八幡の宮司・一宮篤方の娘)
・お鯉の方(徳川吉宗の側室で葵新吾の生母。元は、越前鯖江の町人の娘・お長)
・徳川吉宗(江戸幕府第8代将軍、元・越前鯖江藩3万石藩主の松平頼方)
・水木辰枝(狂言師)
・岡村悪源太(元大阪城代役人・岡村左平太)
・当代(3代目)淀屋辰五郎(かつての大阪の豪商淀屋の没落3代目で奈良の油坂在住)
・須栄(すえ)(淀屋辰五郎の20歳の娘)
・久世大和守(江戸幕府老中で、総州関宿6万石大名)
・松平伊豆守(江戸幕府老中)
・黒田備前守(大阪城代。黒田藩の末流の大名)
・岡本三郎右衛門(淀屋の先祖で、大阪夏の陣での功績に徳川家康から恩賞をもらった材木商)
・土井能登守(娘が久世大和守の妻)
・徳川宗直(御三家筆頭の紀州藩主で、吉宗の従弟・頼致)
・松平左京頼安(徳川一門の伊予国西条藩3万石藩主で、徳川宗直の次男)
・野沢治太夫(紀伊家御用人)
・安藤求馬(紀州家国家老)
・宗田豊之進(紀伊家の正式指南番で、柳生流七剣士の一人)
・穴沢市重郎(柳生流師範代で、紀州藩長期お雇いのお抱え武芸者)
・蓮杖(道成寺門前の末寺・真如院の住職)
・徳川家重(徳川将軍吉宗のお世継で、生母は故・お須磨の方)
・徳川宗武(徳川将軍吉宗の次男で、生母はお鯉の方)
・建部俊雄(柳生流の紀伊家師範代)
・竹内七郎(柳生流の紀伊家師範代)
・栗原喜左衛門(紀州家の大番頭)
・久美(栗原喜左衛門の娘で、穴沢市重郎の許婚者)
・道海(道成寺門前の末寺・真如院の役僧筆頭)
・お力(御坊の街の流れ遊女)
・道念(道成寺塔中の徳願院の住職で、元紀州藩の武士あがり)
・道縁・良智(道成寺塔中の徳願院の僧)
・貝田平十郎(江戸九段下の自源流道場を預かる自源流門生範士)
・武田一真(放生一真流流主の浪人剣士)
・中村半左衛門(紀州家公用人)
・牧野河内守英成(京都所司代で、丹波田辺3万5千石大名)
・桜井吉之丞(松平伊豆守の側近武士)
・柳生俊方(当代柳生流流主7代目)
・和歌山藩の御典医
【第七番】
・葵新吾(越前鯖江藩主時代の徳川吉宗の落胤で長子)
・徳川宗直(御三家筆頭の紀州藩主で、吉宗の従弟・頼致)
・松平伊豆守(江戸幕府老中で、浜松藩藩主)
・安藤求馬(紀州家国家老)
・宗田豊之進(紀伊家の正式指南番で、柳生流七剣士の一人)
・久世大和守(江戸幕府老中で、総州関宿6万3千石大名)
・酒井讃岐守(新任の江戸幕府老中で若州小浜12万石の大名
・水野壱岐守(江戸幕府若年寄)
・本多伊予守(江戸幕府閣老)
・お縫(将軍側室お鯉付きの大奥女中で、秩父八幡の宮司・一宮篤方の娘)
・お鯉の方(徳川吉宗の側室で葵新吾の生母。元は、越前鯖江の町人の娘・お長)
・徳川吉宗(江戸幕府第8代将軍、元・越前鯖江藩3万石藩主の松平頼方)
・徳川家重(徳川将軍吉宗のお世継で、生母は故・お須磨の方)
・高木主水正(江戸幕府の御奏者番で、河内丹南1万石大名)
・太田備中守(徳川家重お付きの江戸幕府若年寄で西丸の責任者。上州舘林5万石大名)
・柳生但馬守俊平(当代柳生流流主)
・野殿杢之助(柳生家の高弟で柳生流七剣士の一人。宗田豊之進とは柳生一門の相弟子の達人)
・宗田豊太郎(宗田豊之進の長男)
・宗田進之助(宗田豊之進の次男)
・お節(宗田豊之進の妻)
・多羅尾平八(柳生流七剣士の一人で、柳生流首席師範)
・萩原勘右衛門(柳生流七剣士の一人)
・中村源兵衛良春(柳生流七剣士の一人)
・物集女藤右衛門(柳生流七剣士の一人)
・柳生六郎右衛門(柳生流七剣士の一人)
・由比三之助(小納戸役。太田備中腹心の青年で、城中筆頭の射撃の名手)
・岡村悪源太(元大阪城代役人・岡村左平太)
・須栄(すえ)(奈良・油坂在住の淀屋辰五郎の娘)
・土岐丹後守(大阪城代、黒田備前守の後任)
・土方河内守(大阪城代加番役で岡村悪源太の義兄)
・谷 出羽守(駿河御城代御加番)
・藤井為之助(大道武芸の集団・藤井為之助一門を率いる)
・大井丹介(藤井為之助一門の早手打ち。佐々木勇斎の古い弟子で、大阪御城代の与力あがり)
・佐々木勇斎(大阪市内ただ一軒の手裏剣鍛冶で、用賀流の忍術師だったが、殺される)
・きく(佐々木勇斎の末娘で、藤井為之助一門の仲間に無理に引き込まれている)
・縄手の八五郎(遠州きっての大親分)
・天神の丑松(縄手の八五郎一家と縄張り争いをする博徒の親分)
・武田一真(放生一真流流主の浪人剣士で、天神の丑松の助っ人)
・井関五郎兵衛(美濃国加納藩の正式剣道指南で柳生流の多羅尾平八門下の師範)
・安藤対馬守(美濃国加納藩大名で元老中)
・綾姫(美濃国加納藩藩主・安藤対馬守の独身の長女)
・雪姫(美濃国加納藩藩主・安藤対馬守の次女で、大垣の戸田右近に嫁ぐ)
・勝姫(美濃国加納藩藩主・安藤対馬守の次女で、江州の堀田出羽守に嫁ぐ)
・吉田次左衛門(浜松藩国家老)
・浜松藩藩医
・松平左京頼安(徳川一門の伊予国西条藩3万石藩主。紀州宰相頼宜の孫)
・真崎庄三郎(江戸神田九段下の自源流道場を任されている元鯖江の薬行商人)
・真崎備前守(武州秩父の大台ケ原の自源流流主)
・美濃国加納藩藩医