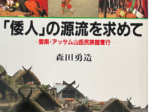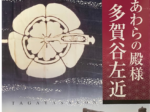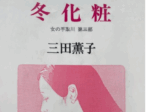- Home
- 北陸地域関連書籍, 「越」関連書籍紹介, 北陸ゆかりの作家による作品
- 北陸ゆかりの作家による作品 第4回 「女の手取川 ー 万屋模様」(三田 薫子 著、創林社)
北陸ゆかりの作家による作品 第4回 「女の手取川 ー 万屋模様」(三田 薫子 著、創林社)
北陸ゆかりの作家による作品 第4回 「女の手取川 ー 万屋模様」(三田 薫子 著、創林社)
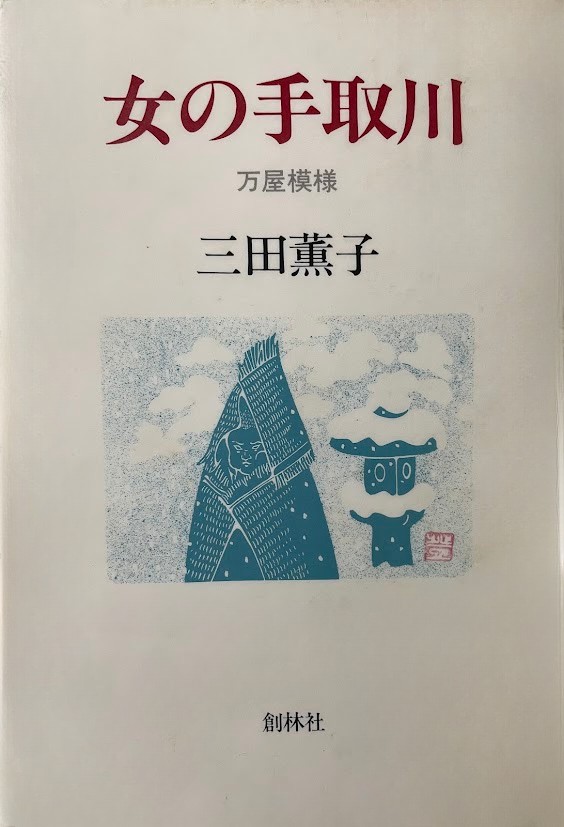
「女の手取川 ー 万屋模様」(三田 薫子 著、創林社、1984年3月発行)
三田 薫子(みた・かおるこ)<本書著者紹介より、本書発刊当時>
1944年、石川県石川郡美川町生まれ、「渤海」同人を経て、詩と小説「あ・うん」の会同人。現在、金沢市在住
本書「女の手取川 万屋模様」(三田 薫子 著、創林社、1984年3月発行)は、白山に源を発する日本有数の急流河川で日本海に注ぐ一級河川の手取川河口の港町・美川町(旧・石川県石川郡美川町、現・石川県白山市美川地区)を舞台に、美川町に生まれ育った女性「七代」を主人公とする大河小説。本書「女の手取川 万屋模様」に引き続き刊行された「緋は紅よりも 女の手取川 第二部」(1985年7月発行、創林社)と「冬化粧 女の手取川 第三部」(1986年6月発行、創林社)とあわせ、「女の手取川」三部作を構成。著者の三田薫子 氏は、本書の舞台となる、石川県石川郡美川町に生れ育ち、著者の母をモデルとした作品で、後半生は小松市に長らく住んだ著名な作家で地方文化の向上のために特に小松市の文化活動の先頭にたってきた作家・森山啓 (1904年~1991年)氏に師事して作家活動を始め、本書が処女作で代表作の一つ。本作品は、1982年11月から1983年4月まで、「北陸中日新聞」朝刊紙上に「泥の歌」と題して、121回にわたって連載され、連載終了後の翌年に単行本として刊行されている。
森山 啓 による評
■地方色の濃厚な、また確固とした実在感をもつ4百枚余の力作である。藩政時代には北前船も出入りして繁栄をきわめた「本吉港」として知られ、天才的作家・島田清次郎の出身地で、手取川大氾濫の際に遭難者たちを幾人も救った無名英雄を出したことでも有名な美川町を活写している。この町の古くからの料理屋・兼魚屋である「万屋」の大勢の全家族と雇人たちの性格を描き分け、主人公の辛抱強くて働き好きな加賀婦人の一典型を見事に造形している。町の生活風習も、よく作品の水鏡に映している。(森山 啓)
本書の主人公は、石川県石川郡美川町の中町通りの商人宿屋と料理屋、魚商を兼ねた「万屋(ばんや)」の娘・七代。七代は、父・平作、母・すまの間の男6人、女3人の次女として、1921年(大正10年)に生まれ、「女の手取川」第一部の本書では、七代が9歳の正月を迎える昭和5年(1930年)から、同じ美川町に嫁ぐ22歳の歳の昭和18年(1943年)春までの時代が描かれる。七代の母・すまは、血縁続きで継子のいなかった万屋の養女で、美川町の織屋の息子だった広川平作と相思相愛で結ばれ、再婚し、七代の父・平作が万屋に婿養子に入る。万屋は、江戸の昔は代々医者で、すまの養父すまの養父の代は、練り薬業を営んでいたが、養父が早死し、平作とすまが夫婦になってから、商人宿屋と料理屋、魚商を兼ねた商売に切り替えた。すまの少女時代は家が落ちぶれ、江戸時代からあった数々の値打ちものの道具を片っ端しからはたかねばならなかったが、平作とすまが始めた商売は繁盛する。
美川町の料理宿・万屋に生れ、少女から娘に成長していく主人公・七代を中心に、賑わい活気があり忙しい「万屋」の大家族をはじめ、「万屋」で働く人たちや、美川町の地域の人たちの人間模様が、昭和初期から昭和十年代の濃密な美川町の地方風俗とともに、生き生きと描かれる。厳格で「万屋」を引っ張rる父の平作や、「万屋」をささえる美しく働き者の母・すまの両親をもつ主人公の七代は、幼い少女の頃から、目を見張る働き者で、頑丈な骨太の体つきは父親そっくりで、すずやかな心持ちは母親そっくりと言われる。年の離れた長兄の平治や次兄の春広、長身でずばぬけた知性の持ち主の三兄・三郎、悪童の弟・清、賢いうえに気立てよく美女の長女・一子、美女で才女の気位の高いお嬢様の末妹・八重垣と、早世した4兄や末弟以外の兄弟姉妹の存在も、非常に大きい。
父・平作が湯殿で倒れ、中風で寝たきりとなり、「万屋」を代りに継いでいく長兄・平次は、平木の郷(現・石川県白山市平木町)から嫁カラを迎えるが、リーダーシップもあり、手取川氾濫の時や、大雪で列車が美川駅で立往生した時などの活躍は素晴らしいが、豪胆さ、雄魂商才に長けた男で、商売でも、運送業にも乗り出したり、更には北海道にも渡り、北海道の魚介類を北陸の地へと送り込んだり、名古屋、大阪方面の市場へ貨車を使って卸す魚の仲買いもし、ますます羽振りの良さを発揮していく。長姉の一子は小松の呉服屋へ嫁ぎ、次兄の春広は、美川町南町のすぐ近所の父方平作の実家である広川家を継ぎ「薔薇屋」という料理屋を始める。三男・三郎は、若い頃から東京日本橋にある薬問屋に憧れていて、朝鮮で一旗あげた美川町出身者の世話でその念願もかない上京し、東京・日本橋の薬問屋に奉公するが、松任での徴兵検査のため、一旦、故郷の美川町に帰り、徴兵検査合格後、金沢の第九師団歩兵第七連隊へ配属され、北支の戦地に赴いていく。
本書の物語は、全14章に分かれ、最初の章「氷室事件」は、七代が9歳を迎えた昭和5年(1930年)正月、2歳年下の弟で5男坊の清と一緒に悪知恵を働かしたことに、父や長兄・次兄から酷く叱責される話。5番目の章は、七代が美川町立尋常小学校高等科2年の昭和9年(1934年)7月の手取川氾濫の話。昭和10年(1935年)以降の昭和恐慌、昭和12年(1937年)盧溝橋事件から日支事変がひきおこされ、9年間に及ぶ戦争に日本が突入していく中、三兄・三郎が昭和17年(1942年)5月戦死。この年の秋に、長兄・平次が独断で七代の嫁入りを決め、七代の身にも大きな転機がやってくる。相手の家は、美川町一番のにぎやかな大通りである大正通りの真ん中にあり、人も使って農業機械の商いを営んでいる家。結婚相手の夫になる男は、大正3年(1914年)生まれで七代より7つ年上。同じ美川町にいても顔を見たことがなく、近衛の曹長で、以前は満州にいたが、その後、支那の戦場に移り、一時除隊となっていた。本書「女の手取川」第一部の最終章は、昭和17年(1942年)秋の七代の結納や、昭和18年(1943年)春の七代の婚儀で締めくくられている。
本書の主舞台となる美川町(旧・石川県石川郡美川町、現・石川県白山市美川地区)は、白山に源を発する日本有数の急流河川で日本海に注ぐ一級河川の手取川河口の港町で、慶長5年(1600年)から明治4年(1871年)まで「本吉(もとよし)」と呼ばれ、明治5年(1872年)には、石川県の県庁所在地となったことがあるが、その時に「美川(みかわ)町」と改名。王朝時代の越中、越前、越後の三湊のうち、越前比楽(ひら)湊は、この地<美川町平加>と今に伝わり、また鎌倉時代の三津七湊の一つに加賀本吉湊が挙げられてもいる。江戸時代になると、雄の魂ふるいたたせた銭屋五兵衛、木屋藤右衛門などの率いる北前船が、日本海で活躍するようになるが、北前船のような巨船は、河底の浅い本吉港に入ることができないため、沖がかりとなり、年間1500艘もの大船が出入りして、加賀藩の米倉も置かれ、小廻りのきく船などで当時の本吉港は大賑わいであったと言い伝えられる。”七代はこんなにも躍動感あふれる海と河口の町の子に、自分を産んでくれた母のことが慕われてならなかった”とも著者は記していて。美川町生まれの著者の思いが溢れている。
賑わい活気のある「万屋」の様子をはじめ、藩政時代、北前船で賑わった港町おらしい美川地区の町と町の人々の様子も非常に興味深い。万屋の忙しい仕事で雇われ人の働きぶりも詳しいし、「万屋」の宿泊客も、山の大地主、京都の西陣の問屋元の旦那さん、金持ちの旦那衆が好みの女と二人連れ。富山の薬屋など長期に泊まる客、変ったところでは、貧乏画家、田舎手品師、歌舞団の裏方などの宿泊客もいて、また布団部屋もあり、電話工事や公共施設のための人夫など多くの客が宿泊するときのためにもなる部屋もある。戦時中は手取川での演習をする兵隊たちが宿泊したりもしている。本吉港も、全国に鉄道が敷設されて自然と衰微し、財をなした海運業者たちのほとんどは、この地を捨て、北海道に居を移していったといわれ、風待ち港での遊郭街は船乗り水夫たちとは切り離せず、その昔は20数軒もあったという遊郭街も、昭和5年(1930年)の段階では少しばかり軒を並べていた程度になってはいたものの、日本海に面した手取川河口の港町・漁師町の美川の町は、豊かな歴史・文化を有し、地域色濃厚な風習の数々は非常にユニーク。
藤塚神社の春季祭として毎年5月に開催され、美川の名物として、今も大変賑わう「おかえり祭り」が一番で、一年のうち、美川町が一番華やぎ活気立つが、本作品でも「おかえり祭り」については、7番目の章を設け、詳しく活き活きと祭りの様子が描かれるが、北前船の栄華を誇った本吉港の時代からずっと引き続いてきている歴史ある春祭り。七代の結納のシーンでも歌われる「御酒(ごんしゅう)」は、江戸時代からこの地に伝承されている祝い歌で、北前船繫栄時代、2月の舟起こし(起舟)の宴に船主の家で船乗りたちによって歌われたもの。「はしか流し」は、米俵の上下についている桟俵を舟代りに、その上に小さな紅白の丸モチを重ね(赤飯を乗せる人もいた)乗せ、赤い小旗をたてて小川に流すしきたりで、はしかの子が発病して高熱のひく10日過ぎ頃、家人がはしかの神様を送り出すために流す風習。天保時代、この町では大家になると、葬式に泣きびとを雇い、皆、共に刳り舟形の朝鮮の木履をはいてやって来たという「天保の風習」も不思議。この地では、精霊流しのことを「流れ冠者」と言い、他にも、美川仏壇や美川のハンカチ・半襟・帯の刺繍といった特産や、「すべり」という美川町特産の珍魚などの紹介もあり。白山奥の木々が、嵐や雪崩などによって手取川の流れに乗り、下流まで流されてくる流木「モーク」が持ちのよい薪となるためにモークを浜で拾う女性たちの場面も挿入されている。
本作品で更に非常に特筆すべきことは、同じ美川町出身の作家で大正文壇にその名を輝かしめた島田清次郎(1899年~1930年)に関する話で、近い時代の地元ならでの話が記されている。本書のストーリーが始まる昭和5年(1930年)に東京で島田清次郎は病死しているが、大正4年(1915年)生まれの近所の屋号が手取屋という床屋の娘・美代子が万屋で七代に島田清次郎の話をする場面がまず登場する。美代子の父は手取屋与市郎で、美代子の自分の祖父の妹が、島田清次郎の義祖母にあたるという関係。島田清次郎の祖母は手取屋与平の娘・里せで、島田清次郎の父の常吉の継母。島田清次郎は手取屋の家族と親しく付き合っているが、本書登場の美代子も、島田清次郎の実母みつを、実家の小川から、「小川のおばさん」と呼び、島田清次郎の母みつの実兄である金沢の西野家で、島田清次郎の葬儀が執り行われたとき、みつに手を引かれ、また、美川の浜の島田家の墓地にも、墓参りに小川のおばさんと一緒に行っている。美川町南町にあった島田清次郎の生家や、美川町での島田清次郎についての噂や悪評判、幼少期の島田清次郎、島田清次郎の内縁の妻・豊などが本書で話題になっている。
美川町の旧町が本書ストーリーの主舞台ではあるが、美川町近郊や手取川上流の地方も生活圏内として関係していて、以下のような話も衝撃的。”山の町、鶴来に「一・六の市」が立つと、海の町の魚屋は魚を天秤棒で荷なったり、荷馬車や馬車を引いたりして商いにいく。反対に、白山の山奥にある白峰村からも、人々が鶴来の里までおりてきて、山の幸と海の幸を物々交換する。彼らは、炭、干柿、柿、山菜、穀類、藁製品などで取引するのだが、子沢山の貧者などは、毎回、魚の借りが増えていくばかりで金が払えなくなる。ついに、美川町へ帰る魚屋の空の大盤ザルの中に、赤子が放り込まれている事さえあったという。昔、万屋でも白峰から貰い子したこともあった。(万屋の)おさんどんの玉子も巴も、この「市」を徘徊していた周旋屋によって、平次に預けられ、万屋に来ていた。”
目次
1. 氷屋事件
2. 万屋周辺
3. 清次郎の洋人形
4. 海の城
5. 手取川氾濫
6. 三つの風習
7. おかえり祭り
8. どんどろ
9. 一子結婚
10.激戦の地へ
11.雪列車と女
12.兵隊の宿
13.三郎戦死
14.泥のうた
あとがき
<主なストーリー展開時代>
・1930年(昭和5年)正月~1943年(昭和18年)春
<主なストーリー展開場所>
・石川県(美川町、金沢)
<主な登場人物>
・万屋七代(大正10年(1921年)美川町生まれ。商人宿屋と料理屋・魚商を営む「万屋」の6男3女の次女)
・万屋平作(七代の父。元陸軍軍人で日露戦争で負傷。実家は織屋をしていた美川町の広川家で万屋に婿養子)
・万屋すま(七代の母。血縁続きの万屋の養女で、平川平作とは再婚)
・万屋平次(七代の長兄。平木の郷から嫁カラと結婚)
・万屋春広(七代の次兄。父・平作の実家である広川家を継ぎ、百姓の娘すず子と結婚し、料理屋を営む)
・万屋一子(いちこ、七代の長姉、寅年(1914年)生まれで、昭和12年(1937年)小松の呉服屋に嫁ぐ)
・万屋三郎(七代の3兄。東京・日本橋の薬問屋で働く。昭和13年(1938年)に金沢の師団に入営)
・万屋四郎(七代の4兄ながら、早世)
・万屋清(七代の弟)
・万屋八重垣(七代の末妹)
・万屋九郎(七代の末弟ながら、早世)
・カラ(平次の嫁で。平木の郷から美川町の万屋に嫁ぐ)
・太平(たいへい、平次とカラの間の長男)
・道子(平次とカラの間の長女)
・すず子(春広の妻で、大きな百姓の娘。元バスガール)
・一子の夫(小松の呉服屋の息子で銀行員)
・玉子(万屋のおさんどん。白峰の山奥から来た山間部の貧しい炭焼人の娘。七代より4歳ほど年上)
・巴(万屋のおさんどん。桑島(現・白山市桑島地区)の山村から来た農家の娘。七代より4歳ほど年上)
・万屋七代の亡き祖母
・通称だご屋の美代子(大正4年(1915年)生まれ。屋号は手取屋の床屋の娘)
・初(手取美代子の姉)
・島田清次郎(1899年~1930年)
・手取与市郎(美代子の父)
・手取与市郎の妻
・みつ(島田清次郎の母)
・豊(島田清次郎の内縁の妻で、山形県西田川郡大山町出身)
・美川町北町の宮古屋という酒屋(七代の叔父で母すまの弟の家。七代の弟・清が以前、養子に出た家)
・ハル(清の養母で、宮古屋の妻。浪花から美川町に嫁ぐ)
・島田清次郎の生家の場所の釣り舟宿の40代終わりの女性
・美川町立尋常小学校の教師や生徒たち
・七代の家の近所の洋菓子屋の老職人
・七代の家の隣近所の男衆や親戚の人々
・ある山の大地主
・京都の西陣の問屋元の旦那
・美川町の竹多家(紺屋勇三郎が藩から賜った苗字)
・美川町の水瀬家(農具で儲けたと言われる洋館)
・美川町北町の「丸久」の薬屋(中町の「万屋」の裏側ある店)
・藤塚神社の氏子総代
・小女郎松と呼ばれた蓮如の松の傍らに住みついた一人の老婆
・尋常小学校4年生ぐらいの一団の悪たれ小僧たち
・下町のやかまし屋で通った名物女
・芸者浜奴、雪舟など(春広に惚れた女性)
・万屋急配部の3人の運転手
・福井の警察
・美川町役場の職員
・町の翼賛壮年団の会合で、講師として統制経済の説明をする県庁の役人
・美川駅の駅長と駅員
・美川駅で大雪で立ち往生した列車乗客の一人の夫人
・手取川の河原に演習に来た兵隊の上官・上等兵・初年兵
・吉原釜屋(現・石川県能美市)からの荷車で西瓜を売りに来る女性たち
・万屋三郎の戦友で美川町近在の人
・万屋の裏の勤め人(薬屋丸久の隣家)の夫人
・万屋三郎をとりあげた、すまと気安い間柄の産婆
・美川町一番の商い屋の主人で、万屋平次と仲の良く、始終、万屋に出入りしている男