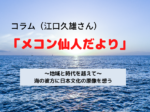- Home
- コラム「メコン仙人だより」(江口久雄さん), 特集テーマ記事
- コラム「メコン仙人だより」(江口久雄さん) 第65話 「面土国とはジャバダイのこと」
コラム「メコン仙人だより」(江口久雄さん) 第65話 「面土国とはジャバダイのこと」
- 2005/12/10
- コラム「メコン仙人だより」(江口久雄さん), 特集テーマ記事
コラム「メコン仙人だより」(江口久雄さん)
第65話 「面土国とはジャバダイのこと」
オオクニヌシ(大国爾支)の委奴(伊都)国が漢に朝貢してからちょうど50年後の107年、倭の面土国王帥升(シュリ・ソーティ)が漢に朝貢します。この面土国とはおそらく面水国(ミマナ)に対置する概念を持つとともに、また帥升(シュリ・ソーティ)とそれを支えるインド系の勢力がこの国に対して抱いていたサヴァドゥィー(稲の洲)という概念が、漢に差し出す国書において「面土国」と漢訳されたのではないかと思います。結論から言ってしまえば、面土国・サヴァドゥィー(稲の洲)・ジャバダイ(邪馬台)は字面や発音は違っていても同じ概念を表す言葉なのですね。
さてオオクニヌシの委奴国を任那連合の再編成のリーダーに押し上げた国土開発は、その後も着々と進んで、ついに稲作経済が海域の通商経済を圧倒する時期が来ました。それが面土国王帥升の漢への朝貢でしょう。「面土国」と名乗ったことからは海上権力国家である任那連合から訣別する意味が読み取れないでしょうか。新田開発が進んで広域のサヴァドゥィーたる「倭ランド」が成立したことで、任那連合の盟主だった委奴(伊都)国に副王をおいて支配すると共に、帥升の漢への朝貢より以降は朝鮮海峡の北を任那(面水国)と呼び、海峡の南を面土国(サヴァドゥィー=倭ランド)と呼ぶ素朴な世界観が、南北は北九州と加羅の国、東西は済州島から北陸までの海域に成立していったのではないでしょうか。後代になって北九州に成立した女王国が大国の魏に対して、漢訳のかつての「面土国」ではなく、対等の立場でジャバダイ(邪馬台)と名乗ったことの淵源は帥升の時代に発するわけですね。
『魏志倭人伝』は魏の立場から書かれているので、倭人の女王がいる国名の表記には卑字が使われました。また伊都国の隣に奴(ド)国の名が見えますが、これは面土国が略された土(ド)国のように思われます。なぜかつての帥升の国に卑字が使われたのかを考えれば、『魏志倭人伝』に、もともと男王がいて70~80年統治したが、ついに倭国が乱れた、と記されている重要な事実に注目する必要があります。魏の立場から倭国の男王を言及する場合は、それはどこの国かわからない倭人の小国の王ではなく、以前に朝貢してきた面土国王帥升のことになります。つまりタミル系の帥升の王統は70~80年続いたことが分かります。2世紀の末期になって倭人の反乱によってこの王統の支配が終わったのですね。新田開発はますます進んで各地に後代の地頭のような倭人の勢力が割拠する戦国時代となったのでしょう。ところで『魏志倭人伝』に見える奴(ド)国の王号を漢音で読んでみますと「シバコ」と読めます。タミル語に「コー(王)」という言葉があります。シバはタミル語のシヴァン(シヴァ神)のことでしょう。シヴァン・コーすなわち「シヴァ王」が漢字表記によって「シバコ」となったものと思われます。帥升の王統が面土国すなわち土(ド)国=奴(ド)国の王位を占めていたことを、このシバコ(シヴァン・コー)という王号が雄弁に語っていると思われませんか。
海人族を中心とする倭人の勢力にタミル人の外洋船(崑崙船・アメノイワクスブネ)がからんで、海中倭人国として倭人の海上権力が成立し、任那の名で漢に朝貢したのが紀元前1世紀の末期のことでした。僕はこの任那を倭人が建てた最初の国だと考えます。任那が漢に使節を送って国際的に国として認知された日が倭国の真の建国記念日ではないでしょうか。その後、任那連合はコーサム韓国のスヴァティによって韓国を中心に再編成され、さらに委奴国のオオクニヌシによって北九州を中心に再編成されました。オオクニヌシに始まる筑後川流域の新田開発はその後もさらなる発展が見られ、ついに稲作経済に立脚した面土国(サヴァドゥィ-)が「倭ランド」として成立、帥升が漢に朝貢することにより、朝鮮海峡の北を任那と呼び、海峡の南をサヴァドゥィー(ジャバダイ)と呼ぶ世界観が成立したのではないかと思います。「面土国」とは漢訳された国書上の言葉で、朝鮮海峡の南北の倭人や韓人は帥升の王統が治める国をサヴァドゥィー(ジャバダイ)と呼び習わしていたのではなかったでしょうか。